| (1) |
床土の準備
 土づくりと輪作により連鎖障害を回避します。完熟堆肥を施用し、吸収量にあわせた適量施肥に努めます。土壌酸度pHは6〜6.5に矯正します。下記はおおよその目安としてください。 土づくりと輪作により連鎖障害を回避します。完熟堆肥を施用し、吸収量にあわせた適量施肥に努めます。土壌酸度pHは6〜6.5に矯正します。下記はおおよその目安としてください。
・極早生〜中早生
 N:P:K=20〜25:20:20〜25kg N:P:K=20〜25:20:20〜25kg
 早生種は元肥主力、中早生は元肥2/3残り追肥。 早生種は元肥主力、中早生は元肥2/3残り追肥。
・中生〜中晩生
 N:P:K=25〜30:25:25〜30kg N:P:K=25〜30:25:25〜30kg
 中晩生種は緩効性肥料を中心に元肥1/2残り追肥。 中晩生種は緩効性肥料を中心に元肥1/2残り追肥。 |
| (2) |
苗作り
 苗質の均一のものを用い、生育をそろえます(発芽を斉一にし、根量の多いガッチリした苗作り)。 苗質の均一のものを用い、生育をそろえます(発芽を斉一にし、根量の多いガッチリした苗作り)。 |
| (3) |
定植
 秋冬作は本葉4〜5枚の苗を、株間33〜35cmに4,500本/10aくらいを目安に定植します。春夏作では本葉5〜6枚のやや大苗を、株間35〜40cm目安に10a当たり3,600〜4,000本程度定植します。 秋冬作は本葉4〜5枚の苗を、株間33〜35cmに4,500本/10aくらいを目安に定植します。春夏作では本葉5〜6枚のやや大苗を、株間35〜40cm目安に10a当たり3,600〜4,000本程度定植します。 |
| (4) |
病害虫防除
基本的にキャベツ、カリフラワーなどと同様の対策を行います。
| 病害 |
症状と発生要因 |
対策と防除 |
| 根こぶ病 |
根に不正形のコブをつくり、コブが肥大すると養水分の吸収が抑制され地上部は日中しおれ、生育が著しく遅れます。畑の菌密度が異常に高い場合など、発病が著しい場合は、収穫にも至らない場合があります。発生は20〜24℃、酸性多湿下で多い土壌伝染性病害。 |
土壌酸性度の矯正、高畝栽培、アブラナ科野菜の連作回避。石灰、チッソとの併用 。 |
| 苗立枯病 |
幼苗期に発生し、茎の地際部が侵され立ち枯れになります。菌の発育は25〜30℃がよく、多湿時に多発します。ピシウム、フザリウム、アファノマイセスの3つの病原菌が関係することが知られています。 |
床土の消毒を徹底します。床土が多湿にならないよう管理します。 |
| べと病 |
冷涼多雨で発生多く、春と秋に激発があります。肥料切れで発生が助長され、品種間差もあります。菌の発育適温は10〜15℃。下葉から発生し、葉脈間に淡褐色、不定形の病斑を生じます。 |
罹病植物残さを圃場周辺に放置しないようにします。 |
| 黒腐病 |
葉縁に葉脈を中心として外側に広がるV字形の黄色の病斑を生じます。菌の発育適温は31〜32℃。乾燥に強く、乾燥条件では1年以上生存可能。 |
アブラナ科の連作を避けます。 |
| 軟腐病 |
花蕾に発生多く、初めは水浸状に変色するが、後に飴色になります。腐敗部は悪臭を放ちます。菌の発育適温は32〜33℃、高温多湿で激発します。 |
連作を避け、。圃場の排水を図ります。 |
| 害虫 |
特徴 |
| コナガ |
年数回発生し、秋から晩秋にかけて多発。早期防除に特に気をつけます。多くのアブラナ科野菜を加害します。葉裏から円形または不規則な形に小さく葉肉だけを食害します。 |
ヨトウムシ類
アオムシ |
1年に4〜5回発生し、春と秋に被害が多い。幼虫の1〜2齢期の防除が重要です。 |
| アブラムシ類 |
モモアカアブラムシ、ダイコンアブラムシ、ニセダイコンアブラムシ。高温乾燥で多発します。 |
ハイマダラノメイガ
(シンクイムシ) |
年に数回発生し、夏〜初秋に被害が多くなります。特に夏季高温、少雨の年には注意が必要です。 |
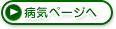 
|
| (5) |
収穫適期
 花蕾の直径が12(Mサイズ)〜14(Lサイズ)cm程度。花蕾重量が250〜300gぐらい。品温の低い内に収穫します。よい花蕾ができるには、栄養生長と生殖生長のバランスが大切で、ブロッコリーは特にバランスの崩れやすい作物のため注意が必要です。 花蕾の直径が12(Mサイズ)〜14(Lサイズ)cm程度。花蕾重量が250〜300gぐらい。品温の低い内に収穫します。よい花蕾ができるには、栄養生長と生殖生長のバランスが大切で、ブロッコリーは特にバランスの崩れやすい作物のため注意が必要です。 |