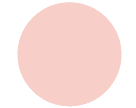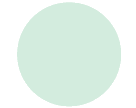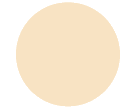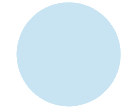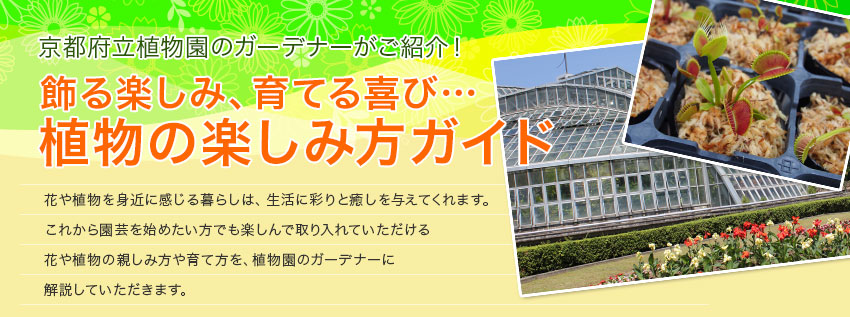- タキイ最前線WEB TOP
- Web連載
- 京都府立植物園のガーデナーがご紹介! 飾る楽しみ、育てる喜び… 植物の楽しみ方ガイド 第10回
2022/07/20掲載
暑い夏がやってきました。この時期、植物園では潅水が一番の仕事となります。どの植物も水を必要としている中、作業面でも水量面でも順番に効率よく回していかなくてはなりませんから、なかなか大変です。それでもひまわりや朝顔が咲き始め、強い日差しの中でも子供たちが夏休みの宿題にと夏の花の観察を始めると、努力が報われたような気持ちになります。今回は少し趣を変えて、そんな子供たちにも人気が高い食虫植物のお話をしたいと思います。
ハエトリグサ〜虫を捕らえる仕組み〜
食虫植物とは、動物あるいは生物由来物の栄養を根以外の器官で消化吸収する植物を言います。ここでは代表的な食虫植物と虫を捕らえる仕組みについてお話しします。
食虫植物としてまず皆さんがイメージするのはハエトリグサではないでしょうか。ハエジコクとも言われ、二枚貝が口を閉じるようにして虫を捕らえて消化します。虫を捕らえる部分は葉が変化したもので、葉の内側表面には左右それぞれ3本のトゲ(感覚毛)があります。葉縁の蜜腺に誘われた虫が、これに触れると細胞内のイオンにより電位差が生じて電気信号が流れます。ただし1回の電気信号では閉じることがなく、30秒以内に2回目の信号が流れると口を閉じる仕組みになっており、これは捕虫葉が虫を確実に葉の中に入れた状態で葉を閉じ、捕らえるための工夫です。

2回目の信号が流れると、開いた葉の中心部の細胞からカリウムイオンが急激に細胞外に流れ出します。そうすると細胞の外のカリウムイオンの濃度が高くなりそれを薄めて均衡を保とうと、今度は細胞内から外へ水が放出されます(これを浸透圧作用と言います)。結果として細胞の内側からの圧力である膨圧が小さくなり、支えを失った2枚の葉はストッパーが外れたバネ仕掛けのように閉じることになります。
モウセンゴケ〜線毛から粘液で捕らえる〜
モウセンゴケは葉から生えた腺毛という組織の先に、ネバネバした粘液をたたえて虫をくっつけて捕らえます。ただ、これだけでは虫に逃げられることもあるので、一部の腺毛が動いて虫を包み込んでいきます。この動く腺毛を触毛と言います。触毛の先に刺激を受けるとハエトリソウと同じ仕組みで、触毛の枝の部分外側にある細胞の膨圧が大きくなり、それに伴い内側細胞の膨圧が小さくなります。結果として触毛は膨圧差で曲がり、虫はもがけばもがくほど触毛に捕らわれていきます。やがて腺毛から酵素を出して虫を消化します。


ウツボカズラ、サラセニア〜落とし穴で虫を捕らえる〜
落とし穴の仕組みで虫を捕らえるものではウツボカズラやサラセニアが有名です。この二つは、ハエトリグサやモウセンゴケと違い積極的に組織が動いて捕虫するわけではありません。壺のような捕虫葉の入口が滑りやすく、内側は登りにくい構造になっており、これで捕虫して内部で消化します。ウツボカズラとサラセニアの違いは消化の方法で、ウツボカズラは内部に消化液をたたえて、この力のみで消化するのに対し、サラセニアは細菌の力を借りて虫を消化します。


ほかにも地中に捕虫組織を持つものや美しい花を咲かせるものなど、食虫植物にはいろいろな品種があります。
7月22日から8月7日まで京都府立植物園では「食虫植物展」を開催します。100種類150鉢の食虫植物を展示しますので、ここであげた食虫植物はもちろん、それ以外のものも観察することができます。
また観覧温室の冷房室や、ジャングル室にも常設で展示しているので、こちらもぜひご覧ください。
-

2026年
春種特集号 vol.61
-
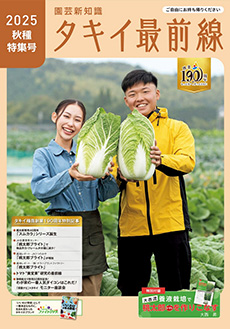
2025年
秋種特集号 vol.60