農業・園芸研究家
町田信夫(まちだ のぶお)
昭和47年より群馬県高冷地の野菜担当普及員を7年、その後キャベツを中心とする園芸試験場高冷地試験地で試験研究に従事し、普及、農家指導などを実践。さらに中山間地域(標高100〜900m)の利根沼田普及、富岡地区農業指導センター、中山間地園芸研究センターを経て退職。現在、長野県の自宅で各種野菜や果樹を栽培出荷する。

定年退職後に野菜栽培を始められる方は多くいらっしゃいます。直売所へ出荷することを目的とした野菜品目の紹介や栽培技術に加え、悠々自適に菜園ライフを実践されている方々の実例にも触れて、趣味で始めた野菜作りを年金以外の実益にするためのノウハウを詳しくご紹介します。
第1回は実際に定年後に農業を始められた長野県在住の2組のご夫妻をご紹介します。このご夫妻の取り組みをとおして、リタイア後の野菜栽培プランのイメージをもっていただきましょう。
2018/02/20掲載
農業・園芸研究家
昭和47年より群馬県高冷地の野菜担当普及員を7年、その後キャベツを中心とする園芸試験場高冷地試験地で試験研究に従事し、普及、農家指導などを実践。さらに中山間地域(標高100〜900m)の利根沼田普及、富岡地区農業指導センター、中山間地園芸研究センターを経て退職。現在、長野県の自宅で各種野菜や果樹を栽培出荷する。


〜長野県在住の、定年後直売出荷で野菜栽培を行っているご夫妻2組に筆者がインタビューを行いました〜
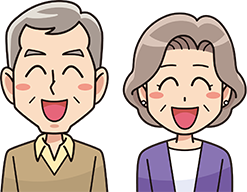
夫妻共に年齢は60代後半、松本市近辺で直売所出荷を主とする農家です。
野菜苗作りは、種子を購入し自家育苗しています。野菜の栽培面積は170a、ほか水稲が30aです。

野菜栽培総面積は170a、アスパラガス、スイートコーン、ニンジンなど多品目を栽培。

ネギの圃場。「松本ネギ」と「赤ネギ」を栽培。
家が兼業農家で妻がずっと農業をしていました。次第に家族が高齢化してきた時、夫が定年になり一緒に農業をすることになりました。
グリーンアスパラガス (農協共撰)30a:6月〜7月上旬収穫、茎枯病防除のため敷きわらと秋になったら茎葉を焼却し菌の死滅を図っています。
紫アスパラガス (農協個選)13a:紫色が鮮やかで食味が良好で、温度が低いと先が開かず、煮るとグリーンになります。

収穫後、養生を始めているアスパラガス圃場。左:グリーンアスパラガス、右は紫アスパラガス。
20a。

長イモは20a栽培。
30a、バイカラー品種を4月中旬に播種し、7月20日ごろより出荷、作る農家が多く販売で競合しています。
15a、「柳川理想」を4月と6月に播種し、9月と11月に収穫します。
10a、「向陽二号」を4月播種し6〜7月に収穫。また他品種ですが、収穫後冷蔵庫に入れ年内出荷するものもあります。
「松本一本ネギ」(地域伝統野菜で、真夏に植え直しをして曲がっているのが特徴です):学校給食向けに出荷しています。給食では曲がっていないネギが使いやすいとのことで、植え直しを行わず収穫します。
赤ネギ病気に強く、分けつしやすい等の特長があります。味のよさと料理に生かせる彩りのよさから導入しています。

ネギは左2条が「赤ネギ」。右は「松本一本ネギ」。「松本一本ネギ」は学校給食向けに出荷している。

ニンジン10a栽培。品種は「向陽二号」ほか。
市内に5カ所あるJA松本ハイランド ファーマーズガーデンの主に1カ所と、2カ所あるイオン直売コーナーのうち1カ所に出荷。ファーマーズガーデンの方は時々他店へも出荷しています。
直売は30年前より無人、有人、出張販売をやっていましたが、現在のファーマーズガーデンやイオンの直売コーナーの出荷形態はやりやすい方式だと感じています。
値決めは、相場やほかの出荷者の様子を見て決定し、早期持ち込み、棚の空き状況を見て途中持ち込みもします。引き取りは閉店間際に行います。ファーマーズガーデンでは、営業時間中に3回メールが入り、売れ行き状況がわかります。


JA松本ハイランド ファーマーズガーデン、市内のイオン直売所などに出荷。
主にファーマーズガーデンで行われる栽培講習会に参加することで情報を得ています。このほかには、種苗店や仲間の農家、雑誌や新聞などから広く情報を集めるよう心掛けています。
松本市、諏訪市、木曽郡からのお客さんが多く、また高速道路など交通の便がよいため、観光客利用も高いようです。
重量野菜の取り扱いは、高齢化に伴い身体の負担が大きくなるので、作物や作型を変更し負担の少ないものを栽培していきたいと思っています。
直売所の出荷販売では、生活できる程度の収益が上がっています。しかし一番大切なことは、購入したお客さんが喜んでくれることです。
法人や個人の直売所、道の駅などに加入している農家が多数います。少量品目や高齢者でも出荷できることが、直売所の魅力です。
農業は天候や作物の病気に左右されることもあり大変な面もあります。けれど、購入してくれたお客さんから「おいしかった」との声を聞き、自分が考えたように作物を作れ、毎年待っていてくれる人がいると張合いになり、これが明日への活力になっています。

佐久市在住の夫妻。共に年齢は60代後半。直売所出荷を主に野菜栽培に取り組んでいます。野菜の栽培面積は60a、このほか水稲を90a。野菜苗は、種子を購入し自家育苗しています。
農家の跡取りとしての使命感、生活の基本は
「ものづくり」にある、子供や孫達に何かを伝えたい、生涯現役を貫きたいと思い始めました。

野菜の総面積は60a(4カ所)での栽培。写真手前から「下仁田ネギ」、ピーマン、水ナス。
畑60a(4カ所)での少量多品目栽培。同一種類野菜の連作を避けるようにしています。
野菜収穫が本格的に始まる前に収穫し、パック詰めやジャムに加工して販売します。

佐久地域では需要の高い水ナスを栽培。
3月播種、6月収穫。前年のキュウリ跡地を利用し栽培します。
佐久地域では需要の多い水ナスを3本仕立ての1本支柱で栽培。
「夏すずみ」5月下旬〜6月上旬定植、7月上旬〜9月上旬まで収穫。
「つるなしモロッコ」5月下旬播種、8月上旬から収穫。
「京波」「フルティカ」をハウスで栽培。毎日収穫しなくてすむため導入しています。
「キタアカリ」「男爵」現在自家用の栽培ですが、いずれはレストランなどに販売もしたいと考えています。
「下仁田ネギ」12月上中旬出荷(販売が安定している)。
一定の需要はあるが大量には売れません。
小花系から大輪系各種栽培し、盆花として出荷します。
ビオラ、キンギョソウなど。レストラン中心に直売所
でも一定量売れます。
「大滝カブ」「飛騨紅カブ」「大野紅カブ」を直売所やレストランへ葉付きで販売します。
「耐病総太り」を栽培。
需要はあるが洗い・荷づくりに手間がかかり本年作っていません。
試験的に出荷したが売れませんでした。
春先の菜花を出荷する予定です。
コマツナ、ラディッシュ、サンチェ、ルッコラ、ミズナ;12月〜1月、4〜5月に出荷します。

キュウリ「夏すずみ」の圃場。収穫は7月上旬〜9月上旬。

インゲン「つるなしモロッコ」収穫は8月上旬より。

ピーマンは「京波」などを栽培。

オクラなども栽培している。
ナス・ピーマン・ネギは、長期間にわたり秋遅くまで収穫できます。主力品目種子は、JAより購入しています。マイナー作物は、1年間試作してから販売し、需要がありそうなものを翌年より導入するようにしています。
JAファーム、道の駅、直売所、レストラン(規格品外)の4カ所で、すべて自宅より4km以内の場所です。品質管理の厳しい所や生産者の自主性に任せられている所などさまざまですが、よい品物は売れると実感しています。
生産物は、全量商品化を目指し残らずお金に換えるため、ニーズや曜日を考慮して適正量を供給するよう心掛けています。搬入は、作業の都合上午前10〜12時です。

JAファーム、道の駅、直売所などに出荷。ニーズや曜日を考慮して出荷量を決める。レストランなどとの契約出荷も行う。
栽培方法の習得は、教科書やネットで調べますが、まず作ってみて、連作・病害虫・作物の特長を覚え、後は観察と経験の積み重ねで習熟していきます。また手間をかけず、無理をせず、あくまでも自然に寄り添い栽培しています。
JR佐久平駅周辺は、人口が増加をしているため良好な販売環境です。
しかし近年、販売競争の激化もあって直売所は、100円ショップ状態になっています。また直売所では、新しい品目が売れない傾向にあります。
(筆者の声:どこも同様な傾向を示しています。都会の直売所は、人口も多く多様な消費者(レストラン等)がいるため目新しい野菜が売れます)。
自分の経営の柱になる魅力的な新品目導入をすることで、農業の重要性や魅力をアピールしたい。また、次代を担う子供達に、農業や食の大切さを伝える方法について模索しています。
直売所の出荷販売では、キャベツやレタスのような大規模栽培とは違い、連作を避け、無駄な経費を削減をすることで、一定の収益が上がっています。
サラリーマン時代には味わえなかった達成感や、作物を作ること、自然の流れの中で生活する心地よさ、改めて食と農業の大切さを実感しています。その一方で、農家が少数派になり、地域の文化や生活が農業を中心に営まれてきた地域コミュニティーの崩壊と衰退を感じます。

今回聴き取りした松本市と佐久市の直売所販売農家は、経験と実践に裏付けされ、実績を上げていると感じました。たぶん多くの失敗と経験を経て、今の形ができてきたと思います。
2組のご夫妻の話をお聞きして、以下のポイントがあげられると思います。
地域の野菜栽培のよくわかる指導者に、指導・助言してもらうのが一番よい方法です。
この度は、定年後に野菜栽培し直売所出荷を行っている人の具体例を取り上げました。実際に直売所出荷ができるレベルの野菜栽培をしていくためには、栽培技術はもちろんのこと、需要の高い品目・品種の選定、年間の菜園計画、労働力の確保(あるいは省力化)など、考えていかないといけないことが多数あります。
次回からは、これらの実例を取り上げつつ、栽培技術や直売所出荷に向いている品目の栽培方法、営農についてなど具体的なノウハウをご紹介していきます。



2025年
春種特集号 vol.59

2024年
秋種特集号 vol.58