
�i��s�b�N�A�b�v
2025/2/20�f��
�g�}�g�u�����Y�u���C�g�v
�_�ѐ��Y�ȕi��o�^�o�蒆�i�i�햼�FTTM178�j

�i��s�b�N�A�b�v
2025/2/20�f��
�g�}�g�u�����Y�u���C�g�v
�_�ѐ��Y�ȕi��o�^�o�蒆�i�i�햼�FTTM178�j

�ߔN�̋C�ۏ����͉��g����ُ�C�ۂ���ԉ�����X���ɂ���A�g�}�g���Y�n�ւ̉e�������X�ɑ傫�Ȃ��̂ƂȂ����܂��B�������͔|�����ł̐ʕ��̈��苟���̂��߁A�ʎ��i����S�ۂ��Ȃ���A���u�͔|�̂��₷���v�ɒ��ڂ��ĕi����ǂ�i�߂Ă����̂����\����u�����Y�u���C�g�v�ɂȂ�܂��B���ɍ͔|���Ԃ�����������X���ɂ���~�t�͔|�ɂ����āA�d�v�Ȍ`���ƂȂ�u�X�^�~�i�v�Ɓu���ʐ��v���R���Z�v�g�Ɉ琬��i�߂܂����B�������͔|���ɂ����Ă��A�����ێ��ƒ��ʐ������肷��A���B�����Ɖh�{�����̃o�����X��ۂ��A���ʂƂ��č����G�i�������Q�ւ̋����������炷�ƍl��������ł��B
�܂��A�t��ɔ����̑������ωʑ�Ƃ��āA�V�����_�[�O���[���i�����̔Z�Ε����j�̂Ȃ��ψ�Ȓ��F����t�^���邱�Ƃʼn��ωʂ̃��X�N�y����}��܂����B���̂悤�ȃ����̂Ȃ����F�������ʕi��͓��{�ł͂���܂Œ蒅���Ă��܂��A�ʎ��i���ێ��̃X�^���_�[�h�Ƃ��āA������p�����Ĉ琬��i�߂Ă����܂��B
�^�L�C�����_��@���R ����
���ωʂɂȂ�ɂ����ψ�Ȓ��F���������i��ł��B�Â݂Ǝ_���̃o�����X�ɂ����ꂽ�u�����Y�v�n�̐H���������܂��B�ʌ`�͍����L�~�^�Ɏd�オ��A�ʏd210g �O��Ŕ��͂����˔����܂��B����Ɖ��ł̋ʂ̔��������Ȃ��A�ʖ[���ł̉ʂ��낢���悢���Ƃ������ł��B�d�ʂœX�������ɂ�������܂��B

�V�����_�[�O���[�����Ȃ��ψ�ɒ��F��������������߁A���ωʂ̃��X�N�����Ȃ��B
�g�}�g�����t���a�iTy-3a�j�A�t���ѕa(Cf9)�ɑϕa���������ق��A�g�}�g���U�C�N�E�C���X(Tm-2a)�A���g�ޒ��a���[�X1(V1)�A�ޒ��a���[�X1(F1)�ƃ��[�X2(F2)�A���_�a(LS)�ɕ����ϕa���������܂��B
�����������A�X�^�~�i������͔|�㔼�ł��ʎ��i���ێ����e�ՂƂȂ�܂��B���ʐ������ɂ悢�i��ŁA���Ɍ������͔|�����œ��������܂��B
�g�}�g�����t���a�ϕa���ɂ���
�^�o�R�R�i�W���~���}��鉩���t���a�C�X���G���n�A�}�C���h�n�̗��n���Ɉ��肵���ϕa��������܂��B�������A���S��R���ł͂Ȃ��A�A���̓��փE�C���X���N����ɑ��B��}������^�C�v�̑ϕa���Ȃ̂ŁA�͔|���ɂ���Ă͔��a����\��������A�]���ʂ�̍k��I�h���ƒ���I�Ȗ�U�z��g�ݍ��킹�č͔|���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
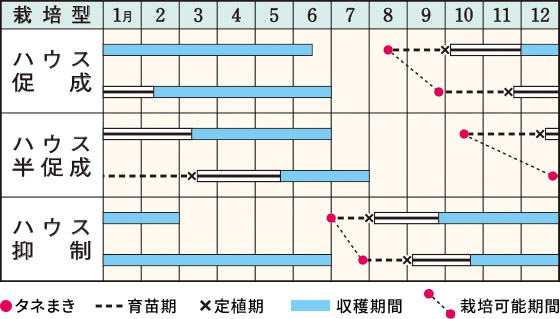
�{��̓X�^�~�i�����邽�߁A���������������Ȃ�X���ɂ���܂��B�ǂ̍�^�ɂ����Ă�����̃`�b�\�����ʂ́A10a������T�s�ȉ���ڈ��Ƃ��A�ǔ�d�_�^�̔�|�Ǘ����s���܂��B
��c���̋ɒ[�ȍ����E�����́A��i�ňُ�ȉԐ��̑�����`���b�N�ʂ̔����A�ԍ������ڗ��Ȃlje����^���܂��B��c�p�n�E�X�́A�z��̐ݒu��Ռ��E�ՔM���ނ𗘗p������������\���ɍs���܂��B�܂��A�������̒�A��^�𒆐S�ɏ��������������ɌX�����ꍇ�́A�ُ��s�i�߂��ˏǏ�j�̔��������O����܂��B�}���͔|�̒�A�c�́A�P�i�Ԗ[���Q���ė���̂��̂�K���Ƃ��A�ɒ[�Ȏ�c��A�͔�����悤�ɂ��܂��傤�B
��A��͂��܂߂Ȋ������s���A�����𑣂����Ƃ��d�v�ł��B��c���㔼����R�i�Ԗ[�J�Ԋ�����܂ł́A�z�E�f���܂t�ʎU�z���s�����ƂŁA�ُ��s�̔������y�����܂��B�u�����Y�u���C�g�v�͔��͂�������̂́A�����ɂȂ肷����Ɖԍ������傫���c��A���`�ʂ��������邱�Ƃ�����܂��̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�{�i�I�Ȋ�����ǔ���n�߂�^�C�~���O�͂P�i�ڂ̉ʎ���500�~�ʒ��x�ɂȂ����������ڈ��ł��B�����������ł́A�ɒ[�Ɋ����ʂ����炷�����͔����A�����_�t�߂̗l�q�����Ȃ���A�������߂ɊJ�n���Ă��������B�����������ɂ����ẮA�ʘH���y�������Ă�����x���K�ȓy�됅���̖ڈ��ƂȂ�܂��B
�ǔ�ʂ́A�t��̏ꍇ�P����`�b�\����10a������0.5�`1.0�s���{���܂��B���̌�͊J�Ԃ��P�i�i�ނ��ƂɃ`�b�\����10 a������1.5�`2.0�s��ڈ��ɉŕ���Ă��������B���ʂ��悢�i��̂��߁A������ǔ�̒x��͑����ቺ�����ł͂Ȃ��A��i�ł̋ʂ̔����ɂ��Ȃ���܂��̂ŁA���߂̔�|�Ǘ��ő����ێ���S�|���Ă��������B
�g�}�g�g�[���̊�ߔ{���͉Ċ���150�{�O��A�~����100�{�O��Ƃ��܂��B�������͓��ɉԂ̐��炪�����̂ŁA�z�����������̊Ԋu�͏T�Q�`�R��ƊԊu���l�߂čs���܂��傤�B�㔼�܂ł������葐�����ێ�����ɂ́A�E�ʂ��O�ꂵ�܂��B�P�`�Q�i�ڂ��R�ʁA����ȍ~�͂S�ʂ�ڈ��ɕK���E�ʂ��Ă��������B
�������̋ɒ[�ȍ����E����������邱�Ƃ͂������A�ቷ���ɂ͉ʎ��̐��n���x���ێ����邽�߁A�H������͑��߂̕ۉ���g�[��S�|����ƂƂ��ɁA�Œቷ�x�̐ݒ�ڕW��12���ȏ�ɂ��܂��B�����̉��x����������15�����m�ۂ��A�K�ȓ����ϋC���̊m�ۂɓw�߂܂��B���x���\���łȂ��ꍇ�A�h�{�����ɌX�������ď��ʌX���ɂȂ�ꍇ�����蒍�ӂ��K�v�ł��B�܂��������Ƃ͂����A�ɒ[�Ȋ����͑����ቺ�������̂ŁA�y�됅���̊����̍����Ȃ��Ȃ�悤�A���܂߂Ȋ����Ǘ����K�ł��B
�u�����Y�u���C�g�v�͎q��������⑽���A�ቷ���ɂ͎q�����������邱�ƁA�����ăV�����_�[�O���[���̂Ȃ��ψ�Ȓ��F���ɂ��ԉʂ��ڗ����Č�����ꍇ������܂��B�ʎ��d�x�͂��Ƃ��Ƃ��������ߓ�ʂɂȂ��邱�Ƃ͏��Ȃ��ł����A�������̉��x�Ǘ��ɂ͒��ӂ��܂��傤�B


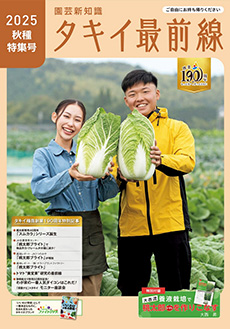
2025�N
�H����W�� vol.60

2025�N
�t����W�� vol.59