
栽培技術
2023/2/20掲載

栽培技術
2023/2/20掲載

農研機構東北農業研究センター 博士(農学) 上杉 龍士(うえすぎ りゅうじ)
本記事の一部は、戦略的国際共同研究推進委託事業(JPJ008837)による成果がもとになっています。
露地野菜の畑に、さまざまな植物を混植すると害虫が減るということは、古くから知られていました。しかし、混植栽培の成否は経験則によるところが大きく、安定した害虫防除に結びつきづらかったところがあります。農研機構東北農業研究センターでは、ドイツの作物連邦研究センター(ユリウス・クーン研究所)、および青森県・宮城県と共同で、混植による害虫防除について科学的な知見を得るための研究を行ってきました。本記事では、タマネギやキャベツの畑にオオムギや開花植物を混植することで安定的に害虫を抑えられるメカニズムについて紹介します。
タマネギとキャベツのオオムギ混植の調査によって、クモ類、ゴミムシ類、カブリダニ類、寄生蜂類、テントウムシ類、ショクガタマバエ、そしてヒラタアブ類などの多様な天敵が見つかりました(第1図)。
混植栽培現場ではさまざまな天敵がみつかったが、東北地方では特に「ヒラタアブ」が目を見張る働きをする






その中でも「ヒラタアブ」の働きが際立っていました。「ヒラタアブ」の成虫は花粉や花蜜を好みますが、幼虫は害虫を捕食する天敵です。「ヒラタアブ」の幼虫がオオムギの上でアブラムシを食べながら増加し、それがタマネギとキャベツの害虫を捕食して減らすメカニズムが明らかになりました(第2図)。アブの幼虫ということで、害虫と見間違えられる不遇な虫ですが、混植栽培において注目すべき益虫です。
オオムギ混植によって「ヒラタアブ」が強化されて、タマネギやキャベツの害虫を攻撃して防除するメカニズム

「ヒラタアブ」は幼虫段階で害虫を攻撃する有望な天敵であるので、畑で見つけたら大事にしたい


タマネギ栽培で最も問題となるのは、ネギアザミウマです。薬剤抵抗性の発達で、効果のある殺虫剤が年々少なくなっている厄介な害虫です。
4月末にタマネギの畝間へオオムギ(リビングマルチ用品種)を播種することでネギアザミウマの増加が抑えられます(第4図)。オオムギ混植によって天敵「ヒラタアブ」が増加することで、「ヒラタアブ」がタマネギの上でアザミウマを捕食して抑えているようです。実際に、「ヒラタアブ」の幼虫の消化管の中からは食べられたアザミウマのDNAが高頻度で見つかっています。
オオムギ混植によってタマネギのネギアザミウマの急増を抑えることができる


通常栽培のタマネギでは殺虫剤の散布を怠るとネギアザミウマの大きな被害につながる。

タマネギの畝間にオオムギを混植している様子。
キャベツ定植と同時に、畝間にオオムギ(リビングマルチ用品種)を播種することで、発生するアブラムシの数が大幅に減少します(第5図)。調査の結果、タマネギの場合と同様に、オオムギ混植によって強化された天敵「ヒラタアブ」がアブラムシを捕食して抑えていることが明らかになっています。
そこで、「ヒラタアブ」の成虫が好む開花植物(ソバ、ハゼリソウ、コリアンダー)を播種した畑を用意しました。するとオオムギ混植のみの畑と比べて、「ヒラタアブ」が増加し、さらにアブラムシ類が減少することが分かりました(第6図)。

キャベツの畝間にオオムギを混植している様子。
オオムギ混植によってキャベツのアブラムシの数を減らす


オオムギと開花植物の混植はキャベツのアブラムシをさらに減らす


キャベツのオオムギ混植栽培は、コナガ・ウワバ類・モンシロチョウといったチョウ目害虫(イモムシ)の数も減少させます(第7図)。中でも、モンシロチョウの幼虫の数が大幅に減少します。またよく見てみると、キャベツへの産卵数自体が減少していることが分かりました。このことから、オオムギ混植でイモムシの数が減った主な原因は、天敵が増加してイモムシを攻撃した効果というよりも、ガやチョウの成虫がキャベツに寄り付かなくなる効果にあることが分かりました。
モンシロチョウは、色やにおいを頼りに産卵場所であるキャベツを見つけます。しかし、オオムギの混植によって、視覚や嗅覚が混乱することで、キャベツへの産卵を防ぐ効果があるようです(第8図)。
オオムギ混植によってキャベツのイモムシの数が減った(特にモンシロチョウの幼虫)



オオムギ混植はモンシロチョウなどの視覚や嗅覚を混乱させているようだ



オオムギ混植は、状況によってはタマネギやキャベツの小玉化を引き起こします。作物への影響を確実に防ぎたい場合は、念のためにオオムギの生長期(播種後1〜2カ月)に1〜2回刈り払いを行った方がよいです。また、刈り払いなしでも作物への影響が出ないような草高の低いタイプのリビングマルチ用オオムギ品種もあります。

4月末に畝間に播種したオオムギは7月中旬には枯れてシート状になる。

オオムギにも虫はつくが、野菜の害虫とはならない
(写真はトウモロコシアブラムシ)。
農林水産省は、日本農業の目指す「みどりの食料システム戦略」の一つとして、2050年までにリスク換算で化学農薬の使用量を半減するとしています。オオムギ混植による露地野菜の害虫防除は、有機農業を見据えた減農薬のための有力な栽培方法の一つとなります。また、畝間へのムギ類の混植は、抑草や土づくりにも効果があります。ムギ類の混植は「リビングマルチ」という名称でGAP(適正農業規範)でも推奨される取り組みです。今後の環境保全型農業での活用を目指した技術開発に期待がもてます。

ブロッコリーとオオムギ・ソバ(開花植物)を混植した減農薬試験の様子。
本記事は、農研機構東北研・市民講座第39回をもとに作成されました。内容はYouTubeで公開されています。豊富な写真や動画などを交えて説明していますので、本記事と合わせてぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=U2SJpeeNSQs


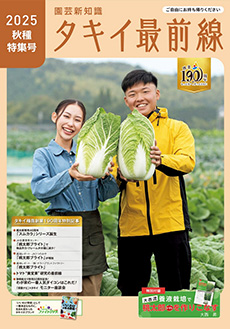
2025年
秋種特集号 vol.60

2025年
春種特集号 vol.59