
栽培技術
2021/6/14掲載

栽培技術
2021/6/14掲載

人気のタマネギですが、真冬に収穫できるセットタマネギが家庭菜園でひそかな人気です。タマネギは5〜6月の収穫で、夏までは出荷も多いのですが、年末になると貯蔵品質も落ちてきます。また、冬場にスーパーで売られているのは北海道産の煮食用タマネギが多く、この時期に収穫できるフレッシュなサラダ用タマネギが人気なのは必然だといえましょう。
ここでは、少しコツのいるセット栽培用品種「シャルム」を使った方法を紹介しましょう。
暖地〜中間地で栽培できます。ただし、中間地では育苗時のトンネルやハウス利用、また冬の訪れの早い地域では12月から被覆資材で保温することが必要になります。
「シャルム」はセット栽培専用種として、揃ってよく太るよう選抜されたF1種です。分球しにくいうえ、耐寒性・耐病性が強く、非常に作りやすい品種です。形状も厚みのある中甲高球で、冬どりとしては多収が望めます。セット球からの栽培なら、弊社通販サイトから秋に、「ホームたまねぎ」として購入することができます。初心者の方が少量から栽培を試される場合は、こちらもおすすめです。
セットタマネギとは、苗からスタートするのではなく、セット球を苗代わりに植え付けることが特徴です。セット球を作るには、まず3月中下旬に播種し、5月中下旬に直径2.5cmほどの小玉で掘り上げます。これがセット球で、夏場は風通しのよい場所で貯蔵し、8月末に圃場へ植え付けます。定植はこのタイミングがベストで、葉を作りつつ肥大の感応が進み、11月中下旬から12月にかけて250g程度の大玉を収穫することができます。

3月中下旬の播種となるので、中間地ではハウス育苗が望ましいでしょう。露地で育苗を行う場合はトンネルを準備しておき、発芽するまで地温の確保に努めます。暖地は露地でも育苗可能です。 よいセット球を作るには、秋まきの育苗の際と同様に完熟堆肥を投入するなどして、肥沃で排水の良好な苗床づくりを行うことです。また、春の上昇気温下での育苗なので、肥料を入れすぎると徒長しやすくなります。葉が倒れるとセット球の充実が不足するため、秋の育苗よりも肥料の量は控えめとします。 本圃1反(10a)分の栽培なら、畝幅130cmほどの畝を40m分用意します。
セット球は、できるだけ同じ大きさで仕上がるようにしたいものです。バラまきより条まきの方が播種密度が揃い、ねらったサイズで仕上げやすいのでおすすめです。条間8cmで短冊状に溝をつけ、株間1cmになるようにまきます。セット球を掘り上げるころには、2〜3条に球が並ぶように仕上がります。

まき終わったら腐熟した堆肥などで覆土し、十分に潅水してやります。その後は苗床を乾燥させないよう、潅水管理を行います。本葉1枚目が伸びたころ、厚まきになった所は間引きます。乾燥させると玉太りが悪く、小玉で終わる場合があるので注意しましょう。4月中旬以降は、可能ならハウスの屋根は降ろし、畝の芯まで十分雨水が入るようにします。
5月中下旬になると葉が倒伏してくるので、セット球を掘り上げます。夏の定植時は直径2〜2.5cmで植え付けるのが最適ですが、収穫して乾燥させると一回り小さくなるので、掘り上げるサイズは2.5〜3cmがよいでしょう。セット球が大きすぎると定植後に分球が増え、逆に小さすぎると貯蔵の際に歩どまりが落ち、また、収量を確保できないことがあります。肥大の程度にバラつきがあるようなら、大きさを揃え2〜3回に分けて掘り上げるとよいでしょう。
掘り上げ後は2〜3日地干しして30〜40球ずつ束ね、夏場は風通しのよい場所で貯蔵します。

1cm株間で播種すると、球が2条にひしめき合うように肥大してくる。

風通しのよい軒下で、葉を束ねてはぜ掛けのようにする。葉を落とし、棚に厚くならないように広げて貯蔵してもよい。
セット球の植え付けは、8月30日を中心としてその前後3〜4日が適期となります。定植が早すぎると葉数分化4〜5枚程度で結球を開始するため、小玉で終わりやすくなります。逆に、定植が9月中旬を過ぎるようでは結球のための日長・温度が足りず、青立ちの不結球が多くなります。
本圃は低温期の球肥大を助けるため、マルチ栽培がよいでしょう。条間20〜25cm、株間10cmの4条栽培とします。深さは、セット球の首が見えるくらいの浅植えの方が、より萌芽が揃います。

A.適期定植。10月中旬までに葉7枚を確保し、球肥大に移る。
B.早植えすると葉4〜5枚程度で日長感応し、小玉で終わる。
C.萌芽が遅れると日長感応できず、青立ちになる。青立ち株は葉つきタマネギとして出荷してもよい。
定植後は1週間で萌芽を揃えることが目標です。9〜10月に十分生育を進め、葉枚数を確保することが、本圃の栽培では最大のポイントになります。
8月末は、まだセット球の休眠が完全に覚めていない状況にあります。そこで、定植の半月ほど前に10℃くらいで冷温処理を行うと、セット球は秋の訪れを感じて休眠から覚め、内部から芽が育ってきます。定植後の萌芽が早まり、また、揃いもよくなる効果が表れます。
(滋賀県タキイ研究農場)

※冷温処理は8/10より、10℃の冷蔵庫で貯蔵した。
残暑の厳しい時期にマルチ栽培を行うので、速やかに発根させる工夫をします。整地の際は十分に水分を含んだ状態で畝立てを行い、マルチがけします。乾燥しやすい時期なので、チューブなどで潅水し、適湿状態にしてから整地するとよいでしょう。定植後もマルチの中が乾かないよう、潅水を行います。 また、地温が高すぎると、萌芽が遅れたり不揃いになったりします。9月初旬になっても暑さが厳しい場合は、寒冷紗のトンネルで遮光をするとよいでしょう。なお、マルチも黒マルチより白黒パンダマルチを利用した方が、地温を下げる効果が大きく発根の促進につながります。

黒マルチでの栽培。

白黒パンダマルチでの栽培。パンダマルチは二層構造で表面が白、内部が黒色。
初期に生育を進めることは大事ですが、チッソ成分を過剰に投入すれば過繁茂となり、軟腐病などを引き起こします。元肥のチッソ量は反当たり15kg程度とし、9月下旬に1回の追肥を行います。チッソの遅効きは球の肥大を遅らせ、青立ちを増やすことになるので、追肥の時期が遅くならないようにしましょう。
植えたセット球が大きい場合は、球の中で生長点が分裂しやすくなり、分球してしまうことになります。このような場合は、植えてから1カ月後くらいの時期に芽かきを行えば、正常な球で収穫することができます。大きい方の株の根が傷まないよう、貧弱な方の株を茎盤の部分で割るように裂いてやれば、簡単にとり去れます。残した方の株には、軽く土を寄せておきましょう。
10月上旬に葉が6〜7枚程度確保できたら、10月中旬には肥大を開始します。この時、マルチの中が乾いているようでは小玉で終わってしまうので、マルチの条間に穴をあけ、しっかり雨水が入るようにしてやります。 寒い地域では、11月中下旬に霜よけのトンネルで保温してやり、肥大を助けて収穫率を高めるとよいでしょう。
収穫は、倒伏したものから2〜3回に分けて行うとよいでしょう。収穫直後は日当たりのよい軒下に置き、乾かしてやります。葉を落とし、凍らないように貯蔵すれば、収穫後1カ月は切り球として出荷できます。 直売所等で販売される方は、より新玉をアピールして、葉つきタマネギで出荷するとよいでしょう。萌芽遅れで青立ち傾向になった場合も、少し基部が太ったものから葉タマネギで出荷すると、出荷率が高くなります。また、葉が傷まないうちに出荷すれば、葉も球もすき焼きなどでおいしく食べられます。

葉つきで出荷される「シャルム」。

セットタマネギとして栽培した「シャルム」。



2026年
春種特集号 vol.61
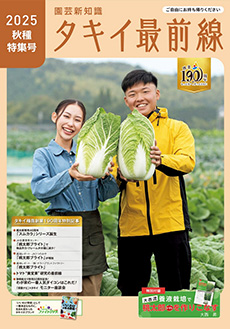
2025年
秋種特集号 vol.60