
栽培技術
2025/2/20掲載

栽培技術
2025/2/20掲載

温暖化によって春から夏にかけての気温が上昇し、トマト生産地では高温による生理障害の一つ“黄変果”の発生が以前にも増して多くなってきています。
そこで、冬春トマト最大の産地である熊本県において、2020〜2022年にかけて実施された大玉トマトの「黄変果の発生に関わる果実温度の条件の解明」と「生産現場において黄変果を抑えつつ可販果率を確保可能な遮光技術」の研究成果について、熊本県農業研究センターの田尻氏にご解説いただきました(編集部)。
熊本県農業研究センター農産園芸研究所 野菜研究室 室長 田尻 一裕
熊本県のトマト促成長期栽培および促成栽培では、4〜6月の高温期に果実の果底部(肩)のみが着色不良となる「黄変果」(図1)が発生し問題となっています。また、この時期の収穫時の着色は約30%と淡く、収穫時の黄変果の判断が困難で問題をさらに深刻にしています。

トマトの赤色色素はリコピンであり、着色不良部位のリコピン含量は少なく、その生合成は12℃以下および32℃以上で影響を受けると報告されています。しかし、黄変果に影響を及ぼす具体的な果実の成熟ステージ、果実温度および遭遇時間は明らかとなっていません。
そこで、各要因が黄変果の発生に及ぼす影響を検討し、黄変果の発生要因を解明しましたので紹介します。
また、 産地では昇温対策として遮光が導入されているものの、明確な遮光開始時期の基準はなく、生育や収量への影響を懸念し、黄変果が発生した後の4月下旬から5月上旬に遮光を開始する場合が多くなっています。
そこで、高温期の黄変果低減技術を確立することを目的に、遮光開始時期の違いが黄変果発生および生育・収量に及ぼす影響を検討しましたので、併せて紹介します。
果実を35℃で96時間加温処理すると、成熟ステージの緑熟期後半から黄変が始まり、催色期にかけて黄変果が発生しました(図2、図3)。


催色期の果実を96時間加温処理すると、32℃から黄変が始まり、33℃で黄変果が発生し、果実温度が高くなるほど、発生程度は大きくなりました(図4)。

また、催色期の果実を35℃で加温処理すると、48時間から黄変が始まり、72時間で黄変果が発生し、遭遇時間が長くなるほど、発生程度は大きくなりました(図5)。

なお、実験は高温期の果実環境を再現するために、室温20℃に調整した室内で、水面をラップで覆ったDigital Water Bath(型式SB-100)の上に果底部(肩)を接触させ各条件に合わせ処理をしました(図6)。

以上のことから、黄変果は、果実が緑熟期後半から催色期にかけて、33℃に96時間、または、35℃で72時間遭遇することで発生します。
そのため、発生を抑制するには、緑熟期後半から催色期までの成熟ステージの果実を33℃以上の高温に上昇させないこと、それ以上の果実温度になっても72時間以上遭遇させないことが重要です。
黄変果の対策として産地ではハウスに遮光資材を展張していますが、明確な開始時期の基準がありませんでした。そこで、生育や収量の確保に、効果的な遮光開始日を明らかにしました。
試験は内張りに遮光率約50%の資材を用いました。遮光により果実の温度上昇が抑制されたことで、黄変果の発生リスクが高い33℃以上の高温に遭遇する時間は短縮しました(表1)。

遮光開始日を3月15日、4月1日、4月15日の3つの条件と無遮光で比較したところ、黄変果の発生量は遮光開始日が早いほど減少することが分かりました(図7)。
これは品種を変更しても同様の傾向になりました。遮光開始が早いほど総収量は少なくなりますが、規格外品(黄変果実)を除く販売可能な果実の収量は4月1日の遮光開始が最も多くなりました(図7)。

また、遮光開始日の違いによって生育や糖度に明確な差は見られませんでした(表2)。

トマトの黄変果の低減を図るためには、成熟ステージ、果実温度、遭遇時間および遮光開始時期が重要ですが、黄変果の発生には品種の影響も大きいので、品種と遮光を組み合わせた対策が必要です。


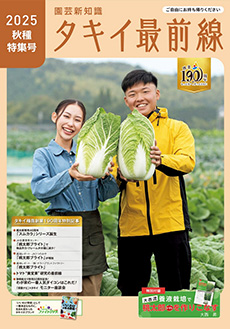
2025年
秋種特集号 vol.60

2025年
春種特集号 vol.59