
産地ルポ
2025/2/20掲載

産地ルポ
2025/2/20掲載

着果は4果に制限。品質維持のため部会では着果数のほかピンチ段数などが決められている。
編集部 2024年6月19日取材
北海道沙流(さる)郡平取町は日高地方の西端に位置しています。町名の平取(びらとり)は、アイヌ語「ピラ・ウトゥル」が由来のように、豊かな自然とアイヌ文化の拠点としても知られています。産業は軽種馬の生産牧場や畜産がありますが、沙流川が作る肥沃な大地と道内では比較的温暖な気候を生かしたトマト生産が中心の町です。トマト栽培は1972年水田転作によって6戸の生産者から始まり年々面積を拡大し、JAびらとり管内の年間取扱高は約1万t、販売額は約36億円を売り上げるまでに発展しました。また、当地ブランドのトマトジュース「ニシパの恋人」は全国的にも知られています。




当地に「桃太郎」トマトが導入されたのは、1985年に元祖「桃太郎」が発売された2年後の1987年。甘熟トマトの味わいを前面に「ニシパの恋人」ブランド名を付け、販売が開始されました。
道内では比較的気候のよい平取町とはいえ、本州のように冬を越しての長期栽培はできません。当地のトマト栽培は低温期から栽培を開始する半促成作型と、夏を越える夏秋作型の2作型に分かれます。JAびらとりでは栽培期間を通じて高品質なトマトの出荷を目指すなか、台木を使用しない自根栽培にこだわりをもって取り組まれています。市場から信頼される品質のよいおいしいトマトづくりが平取トマトの生命線です。

光センサーで糖度も測定される。選果場内の様子。
そうしたJAびらとりの取り組みにおいて今期から新たに栽培品種に加わったのが「桃太郎ブライト」と「桃太郎みなみ」です。今回は特に「桃太郎ブライト」導入の理由について現地取材しました。
近年の温暖化はJAびらとりのトマト栽培にも確実に影響を与えています。選果場を案内いただいた営農生産部の藤本義明次長に「桃太郎ブライト」の導入理由について伺うと、
「近年の高温化により発生頻度の多くなってきた黄変果について市場から対策が求められていました。夏場は熟度の浅いトマトを出荷しますが、従来品種だと本州の量販店に並ぶころにはトマトの肩部が黄変しクレームにつながるケースが増えていました」
販売先の市場や量販店の窓口となる藤本次長には切実な話です。出荷販売担当の新田裕輔課長も「黄変果は平取トマトの評価を落としかねない症状」と同様の苦労を話されていました。
黄変果とは一般的にトマトの肩部が黄色に変色したものを指しますが、果底部の半分以上が黄色のものは規格外品として破棄されます。発生には温度が関係するようで、熊本県農業研究センターの研究によると果実温度が33℃以上で96時間、35℃で72時間続くと黄変果が発生するとされています。近年の温暖化により北海道でも気温30℃を超える日が増え、道内の各産地とも黄変果の発生に悩まされています。この対策としてJAびらとりでは2021年に遮光資材を大規模導入し、2023年には「桃太郎ブライト」の大型試作を実施。黄変果の発生が非常に少ないことや食味性を十分に確認し、2024年より本格導入となりました。

黄変果となりにくい「桃太郎ブライト」の着色に安心感があるという新田課長。

桃太郎ブライト(左)と桃太郎ネクスト(右)。
ショルダーグリーンが残るネクストに対し、全体に色が抜け赤く色が回るブライトの違いがよくわかる。
JAびらとり理事であり平取町野菜生産振興会トマト・胡瓜部会部会長を務める松原邦彦さんは、部会長に就任し4年目を迎えます。松原さんを以前取材したのは2011年で当時33歳。若手生産者の中心メンバーとして青年部を引っ張っていました。当時から平取の寒暖差がもたらす実がしまった「桃太郎」の味へのこだわりは、市場の仲卸業者からも認められていると話され、自身が生産者になった理由を「子どものころから食べることが大好きで、おいしいものを作りたかったから」と幼少期から変わらぬ思いを話されていました。部会長となった今もその思いは変わりません。
「遠くの平取から出荷されるトマトに市場が望むことは味と品質への信頼だと思います」という松原さん。続けて「平取のトマト、『ニシパの恋人』に期待されているおいしさを外したら絶対だめだと思っています。そこは産地として生き残って行くうえで欠かせない」と強い決意を語っていただきました。

松原邦彦部会長
品種導入を検討する際は、部会役員全員で目隠しをして食味検査を実施されます。約140名に及ぶ部会員がいれば、個々の経営環境も異なりますし意見も様々ですが、「味へのこだわり」という共通目標を設定し部会で工夫を重ねられています。実は松原さんは個人的には、現在半促成作型の中心品種である「桃太郎ネクスト」を気に入っておられます。草勢が強く安定し作りやすいうえ食味もよいと評価されています。しかし新品種の「桃太郎ブライト」の方が、誰が作っても黄変果の発生が少なく、硬玉で輸送や店もちの点でプラスになることから、部会全体へもたらす効果が高いと感じておられます。栽培面では2品種で大きな違いは少ないものの「『桃太郎ブライト』は『ネクスト』に比べると地温が低いと根が張りにくい。ただしあまり元肥をドカッと入れると地温が上がった時の芯どまりがおっかない」と、発根剤を利用した樹づくりに取り組まれています。
現在JAびらとりのトマトは9作型あり、大きくは半促成作型と夏秋作型ですが品種の切り替えで出荷全期間を通じて品質を維持されています。また、安定出荷のために収穫段数も上限を設けていますが、2024年から3月定植分は8段から10段ピンチまで延長されました。狙いは8〜9月の出荷量の目減りを避けるためにあります。近年では栽培安定化を目指し、点滴潅水や酸素供給剤、バイオスティミュラントなどの利用が部会内で拡大しています。
46棟のハウスを朝4時過ぎから見て回るという松原さん。自身は反収12t以上を確保されていますが、品質を保ちながら量を確保するのは容易なことではありません。「平取でも高齢化は進んでおり、その分新規就農者が増えてきています。高いレベルで安定して出荷を続けていくことが今後の産地課題です」と部会長として平取全体を真剣に考える姿は13年前に取材した時とブレていませんでした。



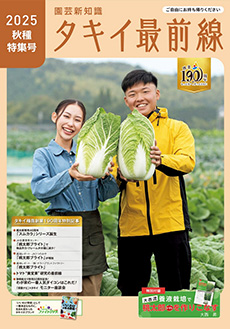
2025年
秋種特集号 vol.60

2025年
春種特集号 vol.59