
�Y�n���|
2025/7/25�f��

�Y�n���|
2025/7/25�f��

�ҏW���@2025�N�P��30�����
���������́A�����x�i1,359m�j�𒆐S�Ƃ����_��R�n�ƁA����ɘA�Ȃ�ɂ₩�ȋu�˒n�т���ъC�݉����ɍL���镽�암����Ȃ��Ă��܂��B����ŕ��n�ɖR�����X�Βn�ōו������ꂽ�k�n�����U���A�唼�̍k�n�͔��n�тƂȂ��Ă��܂��B�����s�́A���������̖k�����Ɉʒu���N�Ԃ̕��ϋC����17.3���A�~���ʂ�2,026mm�A���Ǝ��Ԃ�2,200���ԂƂ������g�ȋC��Ɍb�܂�Ă��܂��B�y����엀�ŁA�s�����S���ɂ��锒�y�̗N���𗘗p���Ĕ��n����������A�l�X�ȍ앨�����萶�Y�ł�����ƂȂ��Ă��܂��B


�����s�L�����ɂ��铇���S���u��O���w�v�͗L���C���������́u���{��C�ɋ߂��w�v�̈�ł��B
JA�����_��L���l�Q����͕����124���ŁA�͔|�ʐς̓���͏t�č͔|����90ha�A�H�~�͔|����80ha�ƂȂ��Ă��܂��B
JA�̎w�j�ŏH�~�ǂ�̔d���8��1���`9��20���܂łɒ�߂��A�o�ׂ�11����{�`�Q�����{�܂łƂȂ�܂��B
�t�ăj���W���̓g���l���͔|��10�����{�`�Q�����{�܂��A�x�^�����͔|�͂Q���`�R����{�܂ł͈̔͂ł��B���n�����͂R�����{�`�U�����{�ƂȂ��Ă��܂��B�ߔN�̓x�^�����͔|�̔d������N�X���܂�AJA�̎w�j��葁���P���d��̐��Y�҂�������悤�ɂȂ�܂����B�䗦�I�Ƀg���l��4�ɑ��x�^�����U�̊����ƂȂ�A�x�^�����͔|�������X���ł��B�t�Ăǂ�̏o�ׂ͂U�������ς��܂łƕ���Œ�߂��Ă��܂��B����͂V���ɓ���ƕi���������Ă���̂ŁA�w�����u�����h�x����邽�߂̎�茈�߂ƂȂ��Ă��܂��B
�L���n��͔̍|�̓����́A�H�~�ǂ�͔|�ɂ����Ă͊Ԉ��������鐶�Y�҂���萔���邱�Ƃł��B�Ȃ��Ȃ珋���̒��Ŕ���������낦�邱�Ƃ��d�����Ă��邩��ł��B���������̊Ԉ�����Ƃ͉ߍ��ł����A�i���̂悢�j���W�����o�ׂ��������Y�҂̈ӋC���݂����������܂��B����ɁA�e���Y�҂͎��n�p�̋@�B��ۗL���Ă���A�K�����n�ł̍��i���m�ۂ�ڎw���Ă��܂��B

�H�~�͔|�ł́A�Ă̍����łW���㒆�{�̔d��͔N�X�������Ȃ��Ă���A�d����̌�i�X���������ł��B���̂��߁A���g�ȓy�n���Ƃ͂����A�X���d�킪�����Ȃ�Ɗ����̌������Ȃ�N�����ǂ�̊������ȑO��葝���Ă��܂����B��^�̌�ނŁA�@�B���n�ɓK�����t�̑ϊ����⍪���̊���ɂ����i�킪���߂���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�L���n��Łu�~�������v�́A�������ł����ꂪ���Ȃ��i��Ƃ��ĕ]�����オ���Ă��܂��B�K�Â܂肪�悢���ߏd�ʂ��o�₷���A���ʐ��ɂ��������Ƃ��ĔN���`�N�����ǂ�̍�^�ō͔|����Ă��܂��BJA�����_��c�_���L���n��c�_�Z���^�[��C�̖{���_���A�L���l�Q�������̐��Y�ґO�c�\�C����́A�u��������R�N�͔|���Ă��邪�A���ꂪ���Ȃ��č��G�i���Ŏ��ʂ��m�ۂł���v�Ɓu�~�������v�̗��_��]�����������Ă��܂��B

�O�c�����9��5���܂���1��28�����n�B����ɂ����ݕސ������邱�Ƃ�A������x�̑傫��������K�l�܂肪�悢�Ɓu�~�������v�Ɋ��ҁB
�O�c����́A�u�~�������v���ȑO��7�p���Ԃō�����Ƃ��ɍ����������Ȃ��ۂ��������̂Ŋ���5�`6�p�Ŕd�킳��Ă���A���͂��傤�ǂ悢�����Ŏ��n�ł��Ă��邻���ł��B
�u����͖{���ɑ�ł����A���̕i��̔���͂��낢�܂��ˁv
����Ȃ��A���낢�������u�~�������v�͗L���n��Ō��݁A�W�����{�`�X�����{�܂��̔N���`�N�����ǂ�ł悢�i������������A�����j���W�����Y�̈ꏕ�ƂȂ��Ă��܂��B
���������s�L�����ł���O���n��͒n�����ɂ����{�݂�����܂����A�O�c����̕ޏꂪ���铒�]�n��͟��{�݂��Ȃ������͓V�����p�ł��B
�u���肪��������^�C�~���O�Ő������邩�ŁA�앿�̑��������܂�̂ł���…�v�Ƃ����O�c����B���H�̂X���O���͉J���~�炸�A�₫�������������ł����A�X��22����66.5mm�̂������肵���~�J������A�T�˔���͏��������������ł��B�u���ɁA8���܂��̔N���ǂ蕪�͊Ԉ������Ȃ��Ƃ悢���m���Ƃ�Ȃ��̂�…�v���̊Ԉ����݂͂Ȃ�����Ƃ��Ƃ�����������ł��B
�u�{�t3���܂ł��厖����������T�C�Y�̎��ɂ����ɒ��J�ɓy�����A���������邱�Ƃ��i���̂悢�j���W�����Y�ɂ͏d�v�ł��v
��Ԃ̂������Ƃł����u�Ԉ����v�Ɩ{�t3���܂ł́u�y�v�̑����b���Ă��������܂����B
����ɁA�O�c�����12���ɑ����~��鎞���ɃJ���V�E���܂�t�ʎU�z����܂��B����͋@�B���n�̂��߂Ɋ����ɑς���t����邱�Ƃ�A�t���ł������č��̑��肪�����Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̍H�v�ł��B�������Ēn���Ɏ��������͔|���A�u�����u�����h�v�j���W�����x���Ă���Ƃ������܂��B
![���n���ꂽ�j���W����J A�����_��L���n��l�Q���I�ʎ{�݂։^�э��܂��B�]���̃~�j�R���e�i�o�ׂɉ����t���R�������p����Ă���B](images/p03.jpg)
���n���ꂽ�j���W����J A�����_��L���n��l�Q���I�ʎ{�݂։^�э��܂��B�]���̃~�j�R���e�i�o�ׂɉ����t���R�������p����Ă���B

�ڎ��ŋK�i�O�������ꂽ��A�I�ʃ��C���ŋK�i�ɕ�������B

�u�~�������v�̏o�ה�������JA�����_��c�_���k����c�_�Z���^�[�L���n��c�_�Z���^�[�̖{���_���B
���̏�Q�i�G�N�{�ǁj�����N�i2025�N�j�͑��������悤�ł��B�N�X�����Ȃ钆�A��^�̌�������i��I���n���̐U���ǂ����{���Ă����\��ł��B�{������́A�Ⴆ�Ώ]���i��ł����̏�Q���������ɂ����u�Ĕn�v���������Ƃ����̂���̍l�������Ƃ��A�܂��A�������ł����肪��r�I���肵�Ă���u���z�v���W���܂��ł͌������ׂ���������܂���A�Ƃ̃R�����g������܂����B���g���ō�^�̌������Ƃ���ɍ��킹�ĕi����đI�肪�K�v�Ȏ����ł��B
�O�c�����32�ŏA�_14�N�ځB��肪�����Ɛ��Y�҂̏W�܂�ɏo�Ă��邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B
�u����̏W�܂�ł͐e���オ�o�Ă��܂��̂ŁA���ŏW�܂�@�������č͔|���C��������Ȃǂ������ł��ˁv
�Ƙb�����O�c����B������Ƃ��ĕi���̂悢�j���W���o�ׂ�ڎw���č͔|���Ȃ���A���܂��܂ȉ\����T������Ă��܂��B
![�L�������]�n��Łu�~�������v����ɂ����L���l�Q�������̑O�c�\�C����B](images/p06.jpg)
�L�������]�n��Łu�~�������v����ɂ����L���l�Q�������̑O�c�\�C����B


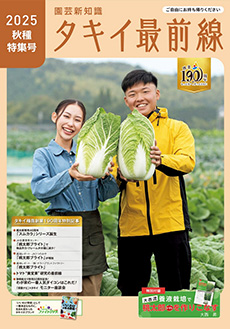
2025�N
�H����W�� vol.60

2025�N
�t����W�� vol.59