
2025/7/25掲載

2025/7/25掲載

JA全農青果センター株式会社本社(埼玉県戸田市)
温暖化による高温や強日照の影響によりトマトのヘタの周りが黄化する現象、「黄変果」の発生が増加し、秀品率の低下が課題となっています。生産者と販売をつなぐ流通の現場から、近年のトマト類の売上高の推移と、黄変果対策としての「桃太郎ブライト」の評価について解説いただきました。(編集部)
JA全農青果センター株式会社 経営管理本部 経営企画部 経営企画課 課長 熱田 智紘
JA全農青果センター株式会社は、日本全国の産地から仕入れた青果物を生協・量販店・外食企業などの実需者へ直接販売することを主な事業としています。「おいしい!その笑顔のために」のキャッチコピーのもと、全国の消費者に安心安全な国産青果物を届け、国産青果物の安定供給と消費拡大に貢献しています。
数ある品目の中でも、当社の売上高No.1は「トマト類」です。2001年度は107.7億円でしたが、2015年度には200億円を超えるまで伸長し、2023年度は211.7億円の売上高となりました(図1)。また、「大玉トマト」・「ミニトマト」に分類しても、2023年度で売上高1位は「ミニトマト」(111.2億円)、2位は「大玉トマト」(100.5億円)であり、トマト類が会社の売上げの中で大きな割合を占めています。

当社の取り扱いにおいて、2017年度までは「大玉トマト」が1位でしたが、2018年度に「ミニトマト」が逆転しました(図2)。「ミニトマト」が伸長した理由として、食味のよさや利便性、値ごろ感のある売価に合わせた量目での商品化などにより消費ニーズに応えられたということが考えられます。一方、「大玉トマト」は、栽培の難易度の高さから異常気象の影響をより多く受け、出荷数量の不安定さや品質・食味のバラツキが散見される状況が続いていたことにより、近年の売上高は頭打ちとなっています。

初期生育時に高温が続く異常気象の影響により、トマトの栽培では着果不良や裂果、黄変果などの発生が増加しており、厳しい栽培環境で作ることが大きな悩みとなっていると全国の生産者から相談を受けます。
近年消費者に支持されるトマトは、「見た目」が重要視される傾向にあり、量販店でも“黄変したトマト”は店頭に並べていただけないケースが多く、当社でもトマトを小分け包装して納品する際は、“黄変していないトマト”を選別し商品化しています。夏秋時期のトマトの小分け包装は、黄変果発生率が高いことによる歩どまり率の低下が課題となっています。また、原体の納品では、黄変果のトマトは販売先からクレームを受けることが多々あるため、その対策として納品前の検品作業を実施するなど、必要以上のコストが発生してしまうことがあります。
2024年産の「桃太郎ブライト」は、結果としてこれらの問題の軽減に貢献したと感じています。特に評価として最も注目されたのは「色回りのよさ」でした。長期高温などの異常気象の中でも黄変果の発生は極めて少なく、秀品率が非常に高いことで歩どまり率の向上、検品作業の回数減少、クレームについても大幅に減少する結果となり、販売先からも高い評価を得ることができました。もちろん歩どまり率向上やコスト削減によって、生産単価の向上にもつながっています。
生産者と販売先それぞれが抱える課題に対して、解決の一助となった「桃太郎ブライト」は、今後も自信をもって提案できる品種になると確信しています。

桃太郎ブライト(上)と他品種(下)。
桃太郎ブライトは均一に着色する特性をもち、黄変果になりにくい。

JAびらとりから入荷した桃太郎ブライト。


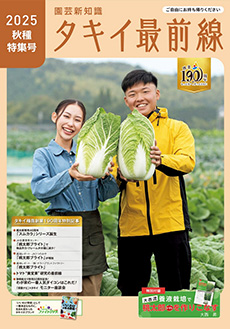
2025年
秋種特集号 vol.60

2025年
春種特集号 vol.59