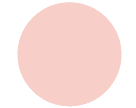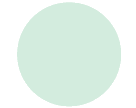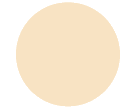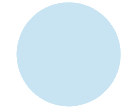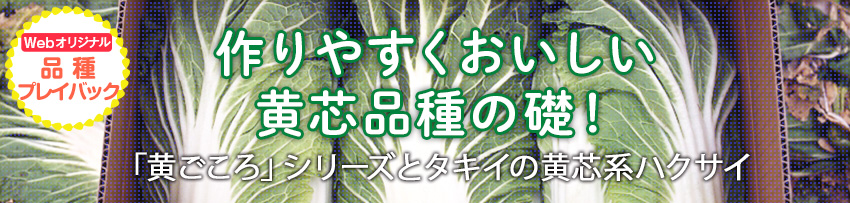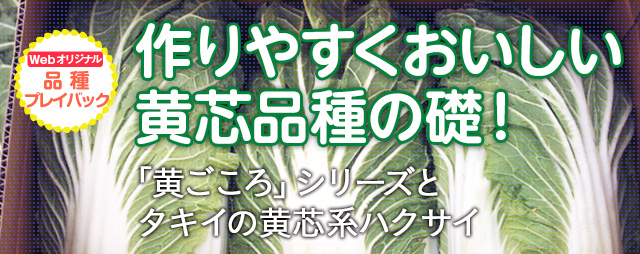- �^�L�C�őO��WEB TOP
- �i��s�b�N�A�b�v
- ���₷���������� ���c�i��̑b�I �u��������v�V���[�Y�ƃ^�L�C�̉��c�n�n�N�T�C
- ���� ���Y�ҁA���ʁA����҂�����Ȃ�x�����u�痼�v�̒a���I
2018/07/20�f��
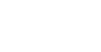 ���i���ƍ͔|�������˔�����
���i���ƍ͔|�������˔�����
���c�n�n�N�T�C�u��������v�̒a��
���{�l�̐H�����Ɍ������Ȃ���Ƃ��ăn�N�T�C�͔̍|������
���{�ł̃n�N�T�C�͔|�̗��j�̎n�܂�͖�������ȍ~�B�Z���Ԃɑ傫�Ȏ��ʂ邱�Ƃ��ł��A�ĐH�Ƃ̑����̂悳����A���̌�͔|�E����͋}���ɑ����A1968�N�ɂ͑S����5��800ha�͔̍|�ʐς�186��7000t�̐��Y�ʂŁA�j��ō��̐��l�ƂȂ�܂����B


�^�L�C�ł�1950�N�Ɏ��ƕs�a�����ɂ�鐢�E����F�P�i��u������z�ꍆ�v�ݏo���Ă��܂��B���̌�A���Ђł�F�P�����i�݁A���̂悳��Nj����đ��푽�l�ȕi�킪���ݏo����Ă����܂��B���̂Ȃ��ŁA���c�n�n�N�T�C���̂́A1960�N��ɕi��Ƃ��Ă͈琬����Ă��܂������A�����̃n�N�T�C�̓J�b�g������Ƃ�1�ʂł̔̔������ʂ������̂ŁA���͂悭�Ă����ʉ��ł����A�s��ɂ͏o����Ă��܂���ł����B�����̎嗬�͋����F�̔����n�N�T�C�������̂ł��B



�Ή��F��u�[��������r���𗁂т����c�n�n�N�T�C
�Ƃ��낪�A1980�N��㔼�ɋN�������Ή��F��u�[���̉e���ŁA���c�n�n�N�T�C��������ڂ��W�߂�悤�ɂȂ�܂��B����ɁA�����l����H�����̉��ĉ��ɂ��n�N�T�C�͔̍|�E����Ɍ������݂��A����܂łP�ʂ������̂��P�^�Q�A�P�^�S�Ȃǂ̃J�b�g�̔������ʂƂȂ�A�����Ō������鉩�c�n�i�킪�܂��܂��D�܂��悤�ɂȂ�܂��B����A�H��ł͒Е��̎嗬���f�Ёi�ʂ��Â��j�����ЂƂȂ�A�H���̂悢���Ƃƌ����ڂ��悢���c�ł��邱�Ƃ̗��������߂���悤�ɂȂ��Ă����܂����B���̔̔����i�́A�]���i��ɔ�ׂĂP�P�[�X������R�O�O�~�̍����������Ƃ�����܂����B

��v�Y�n�ł̎�����d�˕a�Q�����Q�ɋ������c�n�n�N�T�C���J��
�������A�����̉��c�n�i��́A�����ԕa�A��a�Ȃǂւ̑ϕa����A�c����A������A�S�}�ǂȂǂɑ���ϐ�����Q�̓������s�����Ă��܂����B����12�����猵�����ɂ����Ă̍�^�́A��t�ʐς��������߁A�Y�n����͂����₷���A�Ǖi�����萶�Y�ł���i��̈琬�������]�܂�Ă��܂����B
���̂悤�ȗv�]�ɉ�����ׂ��^�L�C�ł́A������Q�̔��������Ȃ��A�N���`�~�ǂ�܂ŕ��L���K�����������������̉��c�n�i��F�P�u��������v�̈琬��i�߂Ă����܂��B�J���ɂ������ẮA���Д_�ꂾ���łȂ��A�uT-666�v�̎��s�ԍ��ʼn��R���∤�m���A�a�̎R���Ȃǂ̎�v�Y�n�Ŏ��쎎�����s���A�c����ǔ����̏��Ȃ��n����I�����琬��i�߂Ă����܂����B
![�J���ɂ������Ă͎���ԍ��uT�]666�v�Ƃ��Đ����{�̎�v�Y�n�ł����쎎�����s��ꂽ�u��������v�B�Y�n�̋~����ƂȂ�ׂ��Y�ݏo���ꂽ�i�B�e�F1996�N2���A���R���j�B](img_chapter1/photo07.jpg)
����Y�n�ł́A�uT-666�v�����߂Ď��삵���ہA�n�N�T�C�̒S���u���[�_�[�����ڕޏ�֕����A�������̐c����ǁi�A���R�j���A�`�F�b�N���邽�߃n�N�T�C����ĉ��ȂǁA���n�ɓx�X�K��ĊJ���Ɏ��g�Ƃ����G�s�\�[�h���c���Ă��܂��B�@
�͔|�̂��₷���Ƃ������������˔��������c�n�n�N�T�C�u��������v
�u��������v�͒��Ԓn�̔N���ǂ�A�g�n�̓~�ǂ�͔|�ɗ͂�����i��Ƃ��ĊJ������܂����B�܂�12���`�P���̌������Ɏ��n����n�N�T�C�ł��B���̓������ȉ��ɂ��Љ�܂��B
- �@������Q�ɋ����͔|���₷���H�~�ǂ�i�����j��
- �H�~�ǂ�ɗp�����钆���i��́A������Ԃ������A�C��̕ω��ɑ傫���e������邽�߁A�ΊD���R�ǂ�S�}�ǂȂǂ̐�����Q�������Ƃ��������₷���Ȃ�܂��B��ʂɂ���܂ł̉��c�n�i��́A������Q�Ɏォ�����̂ł����A�u��������v�͐�����Q�̔��������Ȃ������A���������ō����ԕa�Ȃǂ̕a�Q�ɂ������͔|���₷�����Ƃ������ł��B
- �A�����̒��ł��悭��債�A�d����̕����L��
- �ቷ���ł��悭��債�ϊ����ɂ�������邽�߁A��ʕ��g�n��8�����{�`9�����{�܂�→�N���`�~�ǂ�͔|�܂łƕ��L���K�����������Ă��܂��B�������o�ׂ�ƒ�؉��ł��g���₷�����R�ł��B�@

- �B��Ƃ����₷���ȗ͕i��Ŏ��ʂ��オ��
- �u��������v�͊O�t����v�ő��p�������Ȃ̂ŁA�ǔ�E��U�E�����Ȃǂ̊Ǘ���Ƃ��e�Ղł��B�܂��A���p�͐K����E������̂悢�Z�̉~���`�ŁA���̌`��A�����낢�����Q�ɂ悭�A�G�i���������Ƃ��������������܂��B
- �C�����N���F�ŁA�i�����ɂ߂ėǍD
- �n�N�T�C���J�b�g�����Ƃ��̋��f�ʂ́A���E�E���F�̐F���o�����X���悭�A���Ɍ��������͑N�₩�ȉ��F�݂̉��c�n�N�T�C�ł��B�������A�t�����炩�Ŏ��ꂪ�悭�A�Â݂�����A�Е��p�Ƃ��Ė����悢�̂Ŏs��ł������]�����܂����B���̕i���̍������u��������v�V���[�Y�q�b�g�̗��R�ł��B
�����̎Y�n�̐������Љ�܂��B
���Y�_�Ƃ���́u��������́A�A���R�i�c����ǁj�ɂȂ�ɂ����A���₷���B���ɋʂ��낢���悭�A�K���_�炩���̂Ŏ��n���ɃJ�}������₷���ƍ͔|���E��Ɛ��Ƃ��ɍ��]���B�i���ɂ����Ă��A���Ƀ{�����[����������A�����F�����ɑN�₩�ȉ��c�ŁA���E�E���F�̃o�����X���悭�t���_�炩���H�����悢�v�Ƃ̐��ł��x�s�ꂩ��́w�Е�������̔��������߁A�u��Ќ�����v�ɃT���v���𑗕t�B�]���́u���ɂ��炩�����A���F���N�₩���v�Ƃ悢���ʂł����B�s��ւ̎����o�ׂł��{�����[��������A�i���͂悢�ƕ]����X�ł����x
�iJA�킩��� �c�_�w���� �g���_�T����w���|�V�m���E��؍��x1996�N6�������j


�a�̎R��JA�킩��܁i�B�e�F1996�N�A2���j�B
�w���s��𒆐S�ɔ̔��������ʁA�ق��̉��c�n�N�T�C���200�~�A��ʃn�N�T�C���400�~�����l�ŏ펞�̔��ł��܂����B�J�b�g�ʂ̂��炵���u�Ɣ��Ɖ��̃o�����X�̂悳�v�ƒЕ��ɂ����ꍇ�̒Ђ��₷���A�Ђ��オ��̂悳�������]�����A��x�o�ׂ����s�ꂩ��͂��ׂĘA���o�ׂ̗v��������܂����x
�i���R��JA�������@�o�ˁ@����w���|�V�m���E��؍��x1996�N6�������j


���R��JA�������i�B�e�F1996�N2���j�B
������Q�̔��������Ȃ��͔|�e�ՂŁA�ቷ��含�ɂ�����A�F�N�₩�ŕi���͋ɂ߂ėǍD�B�d����̕����L��������ŁA��Ɛ��Ǝ��ʐ������˔������ȗ͕i��ƂȂ�A���ɂ���܂ŁA������Q�A���ł��c����ǁi�A���R�j�ɔY�܂���Ă��������{�̎Y�n�œ�������܂����B
�Y�n�ł�“�~����“�̂悤�Ɏ�����A�u��������ŃA���R�i�c����ǁj���o��悤�Ȕ��ł̓n�N�T�C�͍��Ȃ��v�Ƃ܂Ō���ꂽ�قǂł����B
-

2026�N
�t����W�� vol.61
-
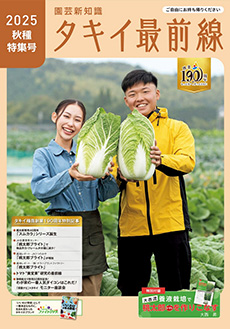
2025�N
�H����W�� vol.60