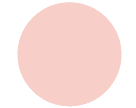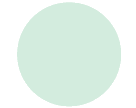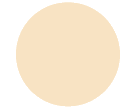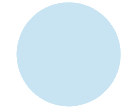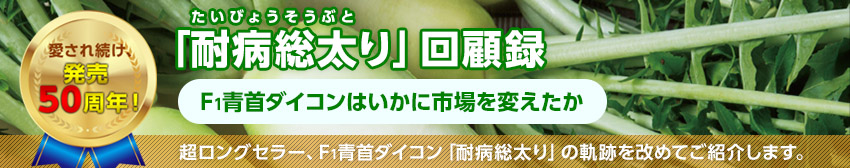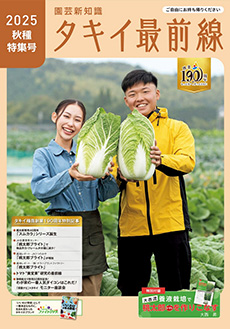2016/02/22掲載
台風がきっかけで「耐病総太り」が三浦半島へ
冬どりダイコンの特産地として自他ともに許してきた三浦半島に、耐病性とはいえ青首の入り込むすきはないという地元民の意識は当然のことと考えられました。ところが昭和54年の秋、大型台風16号と20号が相次いで関東を直撃、特に20号の被害は大きく、三浦半島のダイコンも芯葉のみとなるような壊滅的な被害を受けました。それと同時に台風は思わぬ置き土産を残していったのです。
その辺りの事情は三浦市のダイコン生産農家、鈴木兵七さんの翌55年の記述に、「昨秋の特に10月に襲来した20号台風は大きな爪痕を残して去った。どの農家も転作かまき直しかで迷った末、各人各様に種子探しを始めた。私はたまたま千葉県津田沼の宮坂種苗店のすすめで、『耐病総太り』という立派なダイコンがあることを知り、早速買い入れた。というのは『三浦』の場合、10月中旬以降のまき付けでは良品の出荷ができなかったという過去の経験があったためだ。かといって『耐病総太り』なら万全だとする経験などもちろんなく、ただただ種苗店を信用し、10月22日から栽培に入った。案ずるより産むがやすし、栽培結果は上々で思わぬ成果をあげることができた。第一に割れがなかったこと、第二に抜き取りやすく何回でも間引きしながら良品を出荷できたこと。昨秋まき付けしなかった農家からは羨望の的にされ、目下のところ『耐病総太り』の話題は渦を巻いている」とあります。
台風は華々しく置き土産として「耐病総太り」導入のきっかけを振りまきましたが、その下地は産地自体でぼつぼつ準備されていたと思われます。

全国に「耐病総太り」の名が広がる
神奈川県横須賀農業改良普及所の池谷氏は、青首(「耐病総太り」)導入について「三浦半島は100年近く前から今日まで、1〜2月の厳寒期でも葉の緑は濃く、根部は白く、肉質はやわらかい“冬の三浦ダイコン”として、京浜市場のほぼ70%を占有してきたが、昭和40年後半から少しかたくなったとの声、50年代に入りダイコンとしては大きすぎるという批判が、市場価格を下げる事態になっていた。そこで市場動向に合わせるべく、播種期、畝間、株間など小型化の方向に栽培様式を転換したが、市場価格は必ずしも反応せず農家の反発も高かった。
昭和54年(台風の年)、ごく少数の農家が青首『耐病総太り』の導入を計画、自家採種の『三浦』と交雑を起こさない対策を守るという条件で種子を畑に下ろした。台風の被害にはあったが、まき直しには太りの早いこの品種が適応と判断されて、当初の計画だった30haに追いまきが加わり、同年の青首栽培面積は60haになった。その後台風被害も回復し、まき直しの青首も立派に収穫できた。ところが、販売価格は総平均単価で『三浦』1,111円、青首2,088円で、この価格差が昭和55年の青首『耐病総太り』の作付け急増の主原因となり、昭和56年は青首が『三浦』を上回るような作付けが計画されている」との記述です。

前述の富里村の大竹さんは「例年11月下旬になると関東市場では『尻づまり』から『都』、『三浦』へと移り、『三浦』が出荷されだすとそれまでのダイコンは値下がりするのが通例だが、私の出荷した『耐病総太り』は値下がりしなかった。『耐病総太り』はこれらに十分対応できるということだと思う』といっています。
すでに全国に名が通った「耐病総太り」でしたが、三浦半島に青首「耐病総太り」が入ったという市場へのインパクトは大きく、全国のダイコン産地に伝わりました。そして「耐病総太り」が台風被害から三浦を救ったというエピソードとともにその名を残しました。それは同時に、すばらしい特性をもった地ダイコンとの住みわけに努力した産地の逸話でもあります。
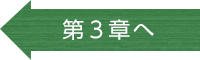
|

|