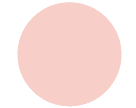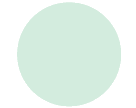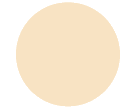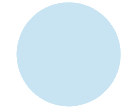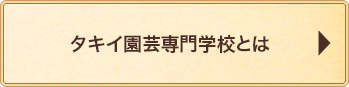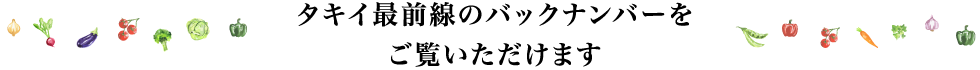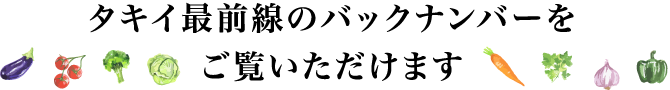第2回
第2回
2016/07/20掲載
2.ブリーダーの仕事を学ぶ
夜間教室
さて、社員である新人時代の私たちは生徒と実習ばかりに明け暮れていた訳ではありません。専門職である品種開発ブリーダーの仕事もご紹介しておきます。
私が入社した昭和45年(万博開催の年)の研究職6名の内訳は、葉菜科2名、根菜科1名、花卉科2名、検定管理科1名で当時としては多めの採用でした。配属先の葉菜科メンバーは私を入れて8名で、4号、5号、8号、10号圃場(総面積5ha)をフルに活用し、当時はキャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、カリフラワー、海外向けの芽キャベツなどを育成していました。


これら十字花科野菜は、博士号を持つ治田場長の自家不和合性※理論により、不和合性遺伝子をⅠ〜Ⅳ型に分類し、二元交配、三元交配、四元交配の採種技術を用いて世界に先駆けてF1品種(交配種)を育成し、国内外向けキャベツ、ハクサイ、芽キャベツの黄金期を築きました。タキイ研究農場が自家不和合性育種で世界の最先端を走っていたのです。
※自家不和合性…同一個体の花粉によって受精が行われない現象
私たち農場の新人は、この理論を場長である治田先生から直に教わることができました。先生から業務終了後に夜間講義を実施していただいたのです。日中の実習で疲れながらも、一言も聞きもらさないでおこうとかじり付いて受講していたことを、つい昨日のことのように思い出されます。治田先生の功績は計り知れませんが、欧州出張で取得した自家不和合性の早期判定法をオランダから導入さたのも先生でした。それまでは交配して50〜60日後に一莢ずつ種子数を調査し、膨大な時間と労力を費やし自家不和合性を判定していました。治田先生によってもたらされた新技術は、蛍光顕微鏡で交配24時間後の花粉管の伸長を調べることで和合・不和合の判定が可能となり、母本数の絞り込みと育成年数の短縮が一気に高まりました。
育種の基本は交配ですが、当時の育種法は自家不和合性と雄性不稔性が主力で、若手社員は十字花科不和合成因子分析法をまず教えられます。これらも定期的に開催される夜間の勉強会で先輩たちから教えられました。
治田場長の教えは見る・観る・看る
入社2年目には、芽キャベツとホウレンソウの育種担当になっていました。当時入社3年までは掛け合わせが記された「調査野帳」も触らせてもらえない時代でしたから、若手に実際の育種を経験させ育てて行こうとする当時の葉菜科長、辻本氏の方針だったと思います。ホウレンソウは昭和45年にF1品種が登場しましたが、市場は固定種が主力でF1品種は依然マイナーでした。そうした状況でしたから、かえって自由に自分の考えで育種ができました。まず、固定種を素材収集し、一般組み合わせ能力検定、次いで特定組み合わせ能力検定と行うことで、育種の基本をこの作物で体得させてもらいました。こうした手順を進めるに当たっては、治田先生著「ホウレン草の栽培」を熟読しました。先ずは素材を2大別して東洋系、西洋系間の組み合わせを実施。次に組み合わせ能力の高い東洋系3グループ、西洋系4グループの特定組み合わせ検定を行い、東洋3系統、西洋2系統が選抜できました。これらが基礎となって、後にタキイ交配品種誕生へと繋がって行きました。
こうして育成中品種の試験採種を農場数カ所で毎年実施していましたが、当時の雌系は半分に雄株が出現してしまいます。この雄抜き作業がF1採種には欠かせない実習でした。私は毎日、早朝5時から専攻生たちにも協力を仰ぎ、雄抜き実習を継続していました。完全に雄株を除去できたと安心して8時の朝礼に臨んでいると、治田先生がホウレンソウの株を手にもってニコニコしながら近づいてこられます。「福嶋君、10号圃場に雄があったよ」と、草丈30cmほどの立派な雄株を渡されました。こちらは時間と人数をかけて抜いているのに、先生はさっと見渡して発見される。こうしたことは一度や二度ではなくほぼ毎日でしたから、先生の目はすごいと感心すると同時に、自分の「観る」目が全然足りないと猛省しました。
治田先生から伝授された、植物を「見る・観る・看る」という3つの「みる」は、年月を経て自分が園芸専門学校の校長となり、生徒たちそれぞれと接する際の土台になったと思います。寡聞にして典拠を明らかに出来ませんが、自然科学は「分類に始まり分類に終わる」と記されておりました。育種も正にその通りだと思います。育種の原点は固定種だというのが今でも私の信念です。
海外で研究の熱気に触れ、ネットワークを築く
昭和40〜60年にかけ、葉菜類は大型産地が全国に誕生し、それに伴い連作による地上部、地下部の病害が各地で大きな問題となりました。次なる私の任務は、土壌病害である萎黄病、根こぶ病、黄化病および地上部病害の黒腐れ病、べと病、白さび病、ウイルス病などの耐病性育種を進めるため、各病原菌の培養・保存法、簡易幼苗接種法、判定法、遺伝子解析、母本維持法の開発を任されました。このため昭和55年に米国ウイスコンシン大学のウイリアム教授の下、1週間にわたる耐病育種研修に参加させていただき、米国の耐病性育種の最新技術に触れることができました。現地では第一線の研究者たちの熱気を体感し、大きな刺激を受けると同時に、育種のためには幅広い素材と先端技術・情報の収集、加えて人脈作りが必要だと知らされたのです。この経験から各病害と各作物の遺伝資源に関し、欧州・米国の主力研究機関に属するトップ3の研究者と交流を図ることに努め、情報や遺伝資源の導入を積極的に図りました。その後も遺伝資源導入には特に力を入れ、欧州、米国をはじめとした各国のジーンバンクと接触し、平成10年までには十字花科蒐集にはほぼめどがついたのです。
余談ですが、当時私が海外に出るにあたって英語など外国語が話せたかというと、日本のほとんどの大学生程度のレベルで正直全くチンプンカンプンでした。それが何とか相手の話すことが理解できるようになるには、同期のアドバイスを実践したことが役立ったのです。その話は稿を改めてご紹介したいと思います。
長沼時代に卒業生と新たな交流
ハクサイ、キャベツの耐病性育種担当を経て、平成元年には北海道の長沼研究農場に赴任し、長日系タマネギ、ホウレンソウ育種に携わりました。北海道の広大な農業生産現場を直に知ることができブリーダーとしてさらに貴重な経験をしました。ドラマのセリフ「事件は現場で起きている」ではありませんが、農家さんそれぞれの悩みを如何に品種に反映出来るかが、ブリーダーの力量だと身をもって教えられたのです。
長沼研究農場時代はタマネギ育成品種推進のため、卒業生を中心に品種試験や現地品種検討会で大変お世話になりました。栽培や採種を快く受け入れていただいた方々は、在学時代の話題になると年齢に関係なく青春時代にタイムスリップできます。寮生活、部屋(生活)顧問との関係、実習、体育祭、ウサギ狩り等々、在学中の話題は尽きず、共に汗した短期間の学校生活が卒業生との絆となり、無理なお願いをも快く引き受けていただいて今でも本当に感謝しています。ブリーダーとして想いが詰まった育成品種を、卒業生が現場で栽培してくれ、その評価から次の新たな品種がまた生まれていく。卒業生対ブリーダーとしての新たな信頼関係が互いに深く構築されていきました。学校が存続する限り毎年の卒業生と指導に当たったブリーダーは、互いを尊重した人として一生お付き合いを続けて行きたいものです。