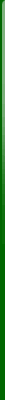 |

ケイトウは、文字どおり太い茎の上に、トサカ(鶏頭冠)のように、燃えるような真っ赤な肉厚の花をつける姿が印象的です。一般的に花と呼ばれている部分は、茎が変化して着色したもので、実際の花はその下に無数に密生しています。歳時記には、秋の日差しの中に、趣豊かないかにも秋らしい感じの草花として記述されています。一般的に秋のイメージが強いのですが、本来高温を好むため、花の少ない夏の草花として見直したい品目の一つです。鮮やかでボリューム感のある花は、観賞期間が長く、夏の花壇を個性豊かに演出してくれます。花色も、赤、黄、オレンジ、ピンクと豊富です。
種類としては、花冠が鶏冠状のトサカケイトウ、鶏冠部分が球状に発達したクルメケイトウ、羽毛を束ねたようなウモウケイトウ、円錐状のヤリゲイトウの4種類に分類できます。さらに草丈が1m以上の高性種から、草丈10〜15cmの極矮性種まであり、高性種は主に切り花や花壇に、矮性種は花壇や容器栽培に利用できます。

熱帯地方原産のため、発芽・生育ともに高温が必要となります。タネまきは、気温が十分に上がった5月上旬以降がよく、7月上旬ごろまで順次行えます。タネは、播種箱にすじまきにするか、6〜7.5cmのポットに2〜3粒ずつまきます。細かいタネですが、嫌光性なので、必ずタネが隠れる程度に薄く覆土します。
発芽まで乾かさないように管理すると、7〜10日ぐらいで発芽するので、生育に応じて間引きをします。すじまきの場合は本葉2〜3枚、ポットまきは5〜6枚になったら、根を傷めないように注意しながら、20〜40cmの間隔で定植します。定植地は、日当たりと排水のよい場所を選びます。
肥料は、生育に応じて速効性の化学肥料や液肥を与えます。高性種は肥料をひかえますが、矮性種は多肥栽培とします。病害はほとんどありませんが、アブラムシやヨトウムシの虫害に注意し、殺虫剤で駆除します。高性種では風などで倒れないように支柱を立てて誘引してやります。
開花も後半になり、色があせてきたら、花穂の部分を切り落として追肥を施せば、秋に再び花を楽しめます。

※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください。 |
 |
|
※時期によってはネット通販に取り扱いのない場合があります。
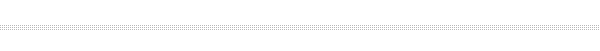 |
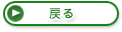 |
|

