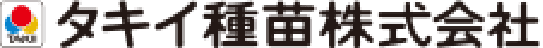調べる

- ホーム
- 調べる
- [野菜]病害虫・生理障害
- [トマト]病名から選択
- トマト半身萎凋病
病害虫・生理障害
 トマト
トマト
トマト半身萎凋病
データ作成年月日:2024/1/26
症状(診断)
本病の症状は極めて慢性的経過をたどる。初め、下位葉の小葉が部分的にしおれ、葉縁は上側に巻く。このしおれは通常2〜3日で止まり、発病部はくさび形に黄白色から黄色に変色する。その後、何日もかかって小葉全体が黄変し、最初に発病した部分から、徐々に褐変、枯死する。病勢の進展にともない、このような症状は次第に上位葉に進み、着果は不良となる。葉柄や茎の導管は褐変するが、萎凋病に比べると不明瞭である。
発生の仕組み
病原:糸状菌(かび) バーティシリウム ダーリエ
病原菌は不完全菌類に属する土壌伝染性の病原菌で、トマトのみに病原性を示す病原菌とトマトのほか、ナス、ピーマンなどに病原性を示すなど複数の系統が知られる。また、トマトを侵す系統について、レース分化が知られ、トマト品種や抵抗性台木のもつ抵抗性遺伝子に対して、現在、レース1〜3の分化が知られる。半身萎凋病抵抗性台木には、レース1、2に対しても抵抗性を示すが、近年、これらに対して病原性を示すレース3の存在が報告されている。
本病原菌は、感染すると、トマトの維管束(導管)に入り込み、維管束を褐変させる。病原菌は、小型分生胞子、大型分生胞子のほか、休眠器官となる微小菌核を形成し土壌中に長期間生存する(10年以上生存するとされる)。罹病作物体中にはこの微小菌核が多数形成され、これが土壌中に残ると土壌中の病原菌密度が高くなり、発病率が増加する。
病原菌の培地上の生育適温は、22〜25℃とされ、30℃でも生育する。発病適温は22〜24℃で、春先から夏にかけてと秋期に発生が多く見られる。やや乾燥した土壌を好み、pHは、アルカリ性に近い土壌を好む。湛水状態が長期間続くと微小菌核が死滅することから水田との輪作では被害が少ない。
防ぎ方
土壌伝染性病害で、罹病植物残さ中に休眠期間となる微小菌核を形成することで土壌中の密度が高くなり、被害が大きくなる。罹病株は根を含めて抜き取り、処分することが大切。土壌中の菌核は、水田にすることで死滅することから、水田との輪作は本病の被害を軽減する。耐病性台木(グリーンフォース、グリーンセーブ、Bバリア)が知られており、接ぎ木栽培も防除に有効である。
発病圃場では、土壌消毒が必要となる。土壌中の病原菌を除去するには、太陽熱による土壌消毒、夏場の湛水によるヒエ栽培が有効である。薬剤による土壌消毒は、クロールピクリン、キルパー、バスアミド微粒剤が利用できる。
注.2003年の改正農薬取締法施行に伴い、「トマト」と「ミニトマト(直径3cm以下のもの)」とは、農薬登録にかかる薬効・薬害の取り扱い上、別個の作物分類に属することになりました。したがって、「トマト」に登録のある農薬を「ミニトマト」に使用される場合は、予め「ミニトマト」に対する登録の有無をご確認ください。
 ご注意
ご注意
文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。
農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。
農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。
本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。
病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。