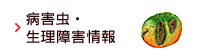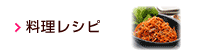調べる

- ホーム
- 調べる
- [野菜]野菜なんでも百科
- [葉根菜]ニンジン
野菜なんでも百科
ニンジン
 種 |
 発芽 |
 花 |
 なり姿 |
ニンジンの家系図(出身地)
アフガニスタンのヒンズークシ山脈とヒマラヤ山脈との合流地点一帯が起源とされています。
13世紀にイランから中国に入り、当時は薬用とされ、野菜として利用したのは16世紀からです。
ニンジンが日本に上陸したのは?
中国から日本へは1600年ごろ渡来し、胡羅蔔(西域(胡国)から渡来したダイコン(羅蔔))と書かれました。東洋系品種は栽培が古く、“滝ノ川”は1716年〜、“金時”は徳川中期に記録があります。欧州系は1796年ごろに長崎市などで栽培され、その後に“長崎三寸”と“長崎五寸”になりました。
F1(一代雑種)品種の育種は1945年に米国で始まり、タキイ種苗から、わが国で初めてのF1種“向陽五寸”が昭和38年(1963年)に発表され、さらに現在“向陽二号”(1985年発表)ニンジンは国内の栽培での主力品種になっています。
世界のニンジンの品種分化
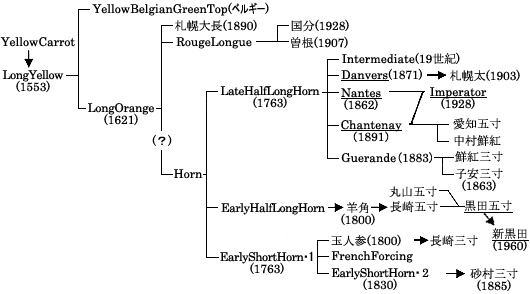
わが国のニンジン分類
セリ科に属する1〜2年性草本で、華北で発達した東洋系と、晩抽の欧州系に大別されます。
| 品種群 | タキイの主な品種 | ||
| ヨーロッパ系 | 三寸 | 平安三寸 | |
| 五寸 | チャンテネー | いなり五寸、向陽二号、恋ごころ、Dr.カロテン5など | |
| 黒田五寸 | 夏蒔鮮紅五寸、黒田五寸、新黒田五寸、グランプリ、優馬、翔馬、オランジェなど | ||
| ナンテス | ピッコロ | ||
| 東洋系 | 金時 | 本紅金時 | |
| 中間型 | 金時と五寸の中間群 | 京くれない | |
ニンジンの住みやすい環境
冷涼な気候を好みます。
発芽適温
15〜25℃とされ、発芽温度は8〜30℃ですが、発芽は35℃以上では発芽しません。低温下では発芽に日数を要し、11℃で20日、8℃では30日以上かかります。
生育適温
18〜21℃で、耐暑性は弱く、これより高温になると根の肥大が悪くなり、根形が崩れ、表皮が粗くなります。同時に葉の成長も鈍り、病気も多発します。低温下では根の肥大が悪くなり、3℃以下では肥大を停止します。
土壌適応性
肥よくな砂壌土が最適です。土は有機質に富み、通気性があり、保水・排水がよく、潅水や強い雨の後表土がかたくしまらない土質が適しています。土壌酸度はpH6.0〜6.6が好適で、pH5.3以下では外葉が黄変し、生育が止まります。
土壌湿度
発芽・根の伸長・肥大・品質・形状・色に大きく影響します。根の生育には土壌容水量70〜80%が最もよく、茎葉の生育はこれより高い方が好適です。湿度が高いと根部の肌が荒れ、極端な場合には根腐れを起こすことがあります。乾燥すると根の伸長、肥大が阻害され、色のつき方も悪く、岐根やひげ根が多くなり、水分が30%以下では生育しません。また水分が不規則に補給されると肌が粗くなります。
ニンジンの生育(夏まき栽培)
| (1)葉数の増加 | … | 播種後、2カ月くらいで8枚前後に達します。 |
| (2)葉重の増加 | … | 50日目ごろから急に増加し、110日目ごろ最大に達します。 |
| (3)根長 | … | 播種後50日ごろに13cm、70日で15cmになります。根長はこの時期までに決定されます。 |
| (4)根の太り(根重) | … | 70日目ごろから急に増大し、110日目ごろまで一直線に肥大、その後緩やかになり、糖分の蓄積、尻の先端の肉付きがよくなります。 |
良質なニンジンとは…
・鮮紅色で色が濃い…カロテン含量が高い(カロテンは体内に摂取されるとビタミンAとなる)。
・尻詰まりがよく、クサビ形、胴細とならない。
・首が細い…芯が細く、肉部が多い。肉重率85%。
・日焼け、青首が出ないもの…吸い込み型。
・皮目(ヒモク)が細かく滑らかで凹凸がない。皮目が縦に並ぶ。
・肌が滑らかでツヤがある。
・根形がそろい、クズが少ない。
・芯が紅色。
ニンジンの着色をよくするには?
| ・ | ニンジンの色の主成分はカロテンで、この色素の生成温度は生育適温よりやや低く16〜20℃です。そのため低温では着色が悪くなり、12℃以下の低温になると着色が著しく阻害されます。7℃以下で生育するとその後温度が上昇して、根が肥大しても着色はよくなりません。また25℃以上になるとカロテンの生成が阻害されるため色ぼけとなります。 |
| ・ | 土壌水分は多湿より乾燥気味のほうがカロテン含量は多くなります。根の肥大も悪くなく、カロテン含量もやや多い70%内外の土壌水分が最適です。 |
| ・ | チッソやカリの不足は一般に生育不良となり、リン酸の過剰な施肥は色を淡くする傾向があります。 |
ニンジンのトウ立ち(抽苔)はなぜ起きるか?
…緑植物感応型(グリーンプラントバーナリゼーション)
ニンジンはある程度の大きさに達した株が10℃以下の低温にあうことによって花芽を分化し(茎の先端にある成長点が発育して、将来花芽となる新しい組織を作ること)、その後の高温長日で抽苔します。
低温感応性は品種によって異なり、一般的に東洋系は敏感で欧州系は鈍感です。東洋系の金時は最も抽苔しやすく、西洋ニンジンのうちでも、暖地に順化した「黒田五寸」などは比較的抽苔しやすい品種です。
植物体の大きさ(第1要因)+ 低温(第2要因)+ 抽苔適温(第3要因)+ 長日(第4要因)
(1)第1要因……早期抽苔株の花芽分化ステージ
| 展開葉数(枚) | 根重(g) | 総葉数(枚) | |
| 金時 | 3〜4 | 3 | 12〜13 |
| 黒田五寸 | 4〜9 | 7 | 16〜20 |
| チャンテネー | 11 | 15 | 19〜22 |
| 中村鮮紅五寸 | 13 | 41 | 21〜25 |
(2)第2要因……10℃以下の低温
(3)第3、第4要因……長日で、10〜25℃で抽苔促進
ニンジンの根部異常症(生理障害)
| 生理障害 | 原因 | 対策 |
| 裂根 | 木部の肥大に篩部の肥大が追いつかないために生じます。根の初期生育が不良で組織が老化した場合、収穫前に急激に肥大する環境下で発生します。 | 保水と排水のよい圃場を選び、有機質を多く施し、土壌の物理性を改善します。追肥は早めに行い、生育後半の急激な肥効は避けます。 |
| 岐根 | ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウが主根を侵したり、主根の直下に多量の未熟有機質や化学肥料が残っていると発生します。ガス害や砕土の不充分も原因となります。 | 殺線虫植物を輪作します。 整地方法(堆肥などの有機質の施用は、播種の1〜2カ月前に行い、よく分解しておく)。 |
| 青首 | 抽根 | 土づくり、適期播種、順調な初期生育を心掛け土寄せを行います。 |
| 白斑症 | 篩部組織に多数の空隙が固まって発生し、表面から白斑状に見える症状です。 地温が低いと根の肥大にカロテンの生成が追いつかないことが原因です。 |
春どりのトンネル栽培で発生しやすくなるため、播種期の検討が必要です。 |
ニンジンの作型と品種
| 作 型 | 栽 培 法 |
| 夏どり栽培 | 北海道、東北冷涼地の栽培で4〜6月に播種し、8〜9月に収穫します。品種としては晩抽性で耐暑・耐病性が大切です。 |
| 秋冬どり栽培 | 7〜8月に播種し、10月から翌年3月ごろまで収穫します。播種から生育初期は高温乾燥期に当たりますが、比較的作りやすい安定した作型です。品種は耐暑・耐病性で形状・色・肥大性にすぐれた多収のものや、耐寒性があり在圃性のあるものが使われます。 |
| 春どり栽培 | 11月中下旬から1〜2月に播種するトンネル栽培。 晩抽で低温肥大性と低温着色性にすぐれ、しみ症などの根部病害に強いと安心です。 |