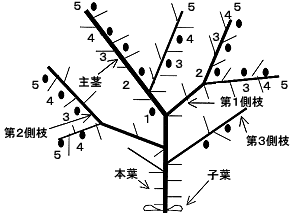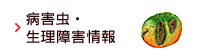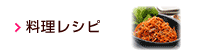調べる

- ホーム
- 調べる
- [野菜]野菜なんでも百科
- [果菜類]ナス
野菜なんでも百科
ナス
 種 |
 発芽 |
 花 |
 なり姿 |
ナスの家系図(出身地)
インド原産と推定されます。インド東部に産するSolanum insanum L.が原産とする説があり、バビロフによれば中国が二次変異中心であるとされます。中国の斉民要術(405〜556年)に茄子栽培、採種のこと、水湿を多く要することなど述べられています。
ナスが日本に上陸したのは?
わが国に渡来した歴史は古く、天正勝宝2年(750年)茄子を進上したという記録があります。延喜式(藤原928年)の耕種園圃の部には営茄のことが詳説してあり、重要野菜であったらしいことがうかがえます。
ナスのことわざ
“一富士、二鷹、三ナスビ"
“嫁に食わすな秋ナスビ"
“ウリの木にはナスビはならぬ"
“おやじの小言とナスビの花は千に一つの無駄が無い"
“女房を質においても初ナス、初カツオ"(ナスを将軍に献上するのが若葉の香る5月始め)
ナスの分類
| 分 類 | 品 種 | 特 性 |
| 千成ナス | 蔓細千成、真黒、山茄、江戸茄、橘田、古河、帯紫、アーリードワーフパープル、ドワーフジャパニーズ、バイオレット | 植物体小さく、横繁性、果実は小卵形。 |
| 長ナス | 佐土原長茄、宮崎長茄、博多長、久留米長、高木長、熊本長、長崎長、薩摩長、津田長、大阪長、燕長、仙台長、川辺長 | 多くは強勢、立性、晩生、肉質は粗い。 |
| へびナス | 支那大長、清国大長、清国水茄、スネイク | 植物体中位、果形非常に細長い。 |
| 丸ナス | 巾着、大丸、芹川、大仙丸、加茂 | 植物体大きく茎太く立性、果実中〜大。 |
| 白ナス | 鹿児島白茄 | 果実白く、植物体はアントシアンの発生がなく緑色。果実は大きく晩生。 |
| アメリカ大ナス | ブラックビューティ、ニューヨークパープル、ジャイアントラウンドパープル、マンモス | アメリカに多く植物体大、果実大型。 |
| 青ナス | 明治の初年中国から導入されたもののようで、果実もへたも葉も紫色を欠き奈良漬に利用される。 |
わが国のナスの品種改良(真黒系の分化―高橋)
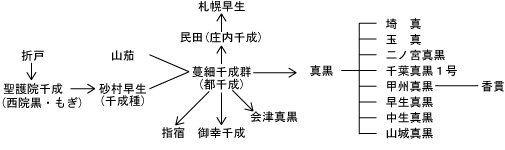
ナスの住みやすい環境
果菜類の中でも、特に高温性の作物です。
発芽適温
20〜30℃とされ、最低限界温度は11℃、最高限界温度は35℃です。ナスの種子は変温操作(昼間30℃、夜間20℃)をするとよくそろって発芽します。
生育適温
昼23〜28℃、夜間16〜20℃。最低限界7〜8℃で、霜には非常に弱くマイナス1〜マイナス2℃で凍死します。最高限界は40℃です。
根の伸長適温
28℃、最低8〜10℃、最高38℃。根毛発生の最低は12℃、最高38℃です。
花粉の発芽、発芽管の伸長
適温は20〜30℃で、最低限界温度は15〜17℃、最高限界温度は35〜40℃です。
光飽和点
約4万ルクスと果菜類のうちでは割合低い部類ですが、弱光下では軟弱徒長となり、花の発育が悪く、落花は多く、果実の発育は悪くなり、果実の着色も劣ります。ほかの野菜に比べて、着色のため特に紫外線を必要とします。
ナス花芽分化および開花結実の生理生態
| (1) | 花芽分化 一般に播種後30日ごろの本葉2〜3枚展開、草丈4cmぐらいの時に花芽を分化し、8〜9葉で第1花を着花します。その後5日ぐらい遅れて第1花の2節上に第2花の分化が認められます。 子葉展開後30日の6〜7葉苗では、6花の分化が認められ、第1花の着生している主茎上に3花、第1花のすぐ下の第8節のわき芽が伸長した第1側枝上に1〜2花、その下の節位の第7節から発生した第2側枝上に1花の分化が認められます。 子葉展開後40日の10葉苗では、21〜23花の分化が認められます。 子葉展開後50日の12〜13葉苗の第1花開花時では、48〜50花の分化が認められます。 実際栽培では3本仕立てがとられ、第1花の開花期までの育苗期間中に36〜37花の花芽が分化していることになります。
|
||||||||||||
| (2) | 開花、結実の生理・生態
|
||||||||||||
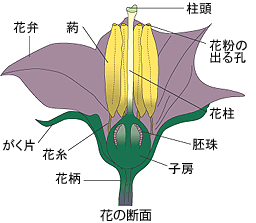 |
|||||||||||||
| (3) | 開花結実の条件
|
||||||||||||
| (4) | 花の形態と結実との関係 正常花は大型で色濃く、花柱が長く、開花時には柱頭が葯の先端より長く突出しています(長花柱花)。そのため柱頭上に容易に受粉されます。しかし短花柱花は柱頭が葯筒内に隠されており、花粉粒はほとんど葯筒内に落花することがなく、柱頭上に受粉される機会が極めて少なくなります。 |