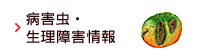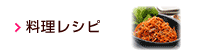調べる

- ホーム
- 調べる
- [野菜]野菜なんでも百科
- [果菜類]インゲン
野菜なんでも百科
インゲン
 種 |
 発芽 |
 花 |
 なり姿 |
インゲンの家系図(出身地)
インゲンの原産地は、中央アメリカとされています。コロンブスのアメリカ新大陸発見以後に世界への伝播が始まりました。ヨーロッパでは、16世紀半ばの栽培記録があります。その後北上し、17世紀末には全ヨーロッパで一般に利用されるようになりました。アジアへは16世紀末に中国に伝わり、インドへは近世に伝播したとされています。
インゲンが日本に上陸したのは?
わが国には、江戸時代に(1654年)中国から隠元禅師によって伝えられたとされています。その後、明治初期に多数の品種が欧米から導入され、冷涼な地域での種実用品種の栽培が広まりました。サヤインゲンは、戦後栽培面積が急増し、現在に至っています。
インゲンの種類
インゲンは利用の仕方や草姿から、次のように分けられます。
| 利用法 | 草姿 | 代表種 |
| 種実用 | つるあり | トールシュガー、穂高、虎丸うずら |
| つるなし | 本金時 | |
| さや用 | つるあり | モロッコ、ケンタッキー101、黒種衣笠 |
| つるなし | 恋みどり、初みどリ2号、さつきみどり2号 |
インゲンの地域による好み
インゲンの消費には地域性があります。関東地方を中心とした地域では、どじょうインゲンと呼ばれる長莢で、やや子実の凹凸が目立つ莢が好んで使われるのに対し、関西地方では、12〜13cmぐらいの中莢で子実の目立ちの少ないスムーズな莢が好んで使われます。
インゲンの住みやすい環境
発芽適温
インゲンは比較的温暖な気候を好み、発芽適温は23〜25℃です。
生育適温
生育の適温は15〜25℃です。栽培可能な気温の範囲は10〜30℃で、10℃以下では生育が停滞し、5℃以下では枯死してしまいます。25℃以上では花粉の稔性が悪くなり、着莢率が低下します。
土壌適応性
土壌の適応範囲は広く、栽培は容易です。排水良好で耕土の深い肥よくな埴壌土で最も良好な生育を示します。ただし、砂土は乾燥と過湿を繰り返すことでストレスを与えやすいので適しません。
土壌酸度
酸性土壌に対しては特に弱く、pH6前後が適当とされています。また豆類の中で、塩分には最も弱い種類です。耐湿性は強くないので、水田土壌などでは排水対策を十分に行ってください。
インゲンの連作障害と対策
インゲンは、エンドウほどではありませんが、連作すると生育が劣り、収量も低下します。このため、2〜3年の間隔で輪作を行うのが望ましい方法です。連作する場合は、土壌消毒を定期的に行うと栽培が安定します。
インゲンの生育
適温下の栽培では、播種後4〜5日で発芽します。つるなし種は本葉が5〜6枚展開すると、主枝と側枝に一斉に花芽が分化します。つるあり種は6〜7節目に花芽分化が起こり、生育とともに上部節位へと移行します。播種後、開花までの日数はつるなし種で30〜40日、つるあり種は35〜45日かかります。開花後、10〜15日で若莢を収穫します。収穫期間はつるなし種で2週間程度と比較的短期間ですが、つるあり種は30〜60日にもおよびます。
インゲンの作型
(近畿)
| 作型 | 播種期 | 収穫期 |
| ハウス栽培 | 1月下旬〜3月中旬 | 4月中旬〜7月中旬 |
| 露地栽培 | 4月中旬〜5月中旬 | 6月中旬〜8月中旬 |
| 露地栽培 | 8月上旬〜9月上旬 | 9月下旬〜11月上旬 |
根粒菌との関係
他のマメ類より根粒菌の着性が悪いので、チッソの控えすぎはよくありません。