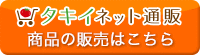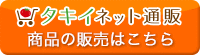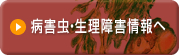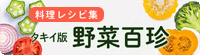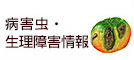ニンジン

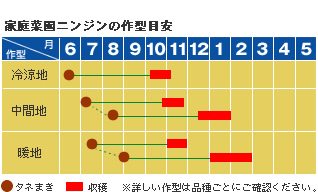
地ごしらえ、タネまき
日当たり、水はけのよい場所を選びます。酸性土を嫌うため、粗起こしのとき、苦土石灰はやや多めに施します。深く耕した後、元肥を全層に施し、土をよく砕いて畝を立てます。ニンジンは生育期間が長いので、元肥には緩効性の肥料を用い、全層に施しておきます。
1m幅の畝なら2条にまき溝をつけ、条まきか点まきにします。タネの吸水力が弱いので、発芽するまで畝を乾かさないよう、敷きわらなどで対処してやります。
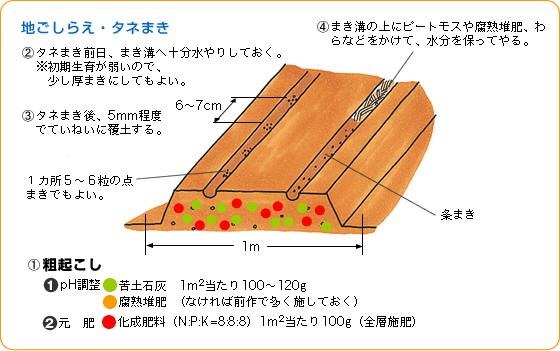
なお、ニンジンの種子には発芽抑制物質があり、かつては播種前にひと晩水に漬ける浸漬処理をして、湿った砂と混ぜてまきやすくして畑にまかれることがありました。しかし、近年はタキイの場合でも、特に発芽抑制物質が多く含まれるタネの毛の部分を取り除き(毛除)、抑制物質が発現しないよう、採種から十分時間をとって出荷されるため、浸漬処理は必要ありません。また、ペレット種子の登場でまきやすさも向上しています。
間引き
1回目の間引きは本葉2〜3枚ごろ、込んだ所を間引いて株間をそろえておきます。ニンジンは初期生育が遅いため、雑草の方が早く大きくなることがあるので、除草は早めにしておきます。本葉5〜6枚になったら2回目の間引きをして、株間を10〜12cmに広げます。
追肥、中耕、土寄せ
1回目と2回目の間引きの後、条間に肥料溝をつけて追肥をし、覆土しておきます。2回目の追肥は根が太り始める時期になるので、遅れないよう施し、肥料への覆土だけでなく、根が露出して肩部が緑化するのを防ぐため土寄せをします。この時、葉の付け根に土が入らないよう、ていねいに土を寄せます。
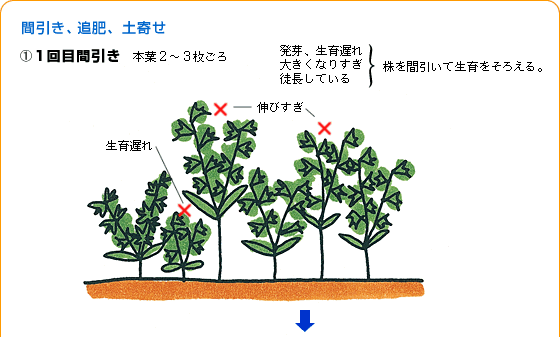
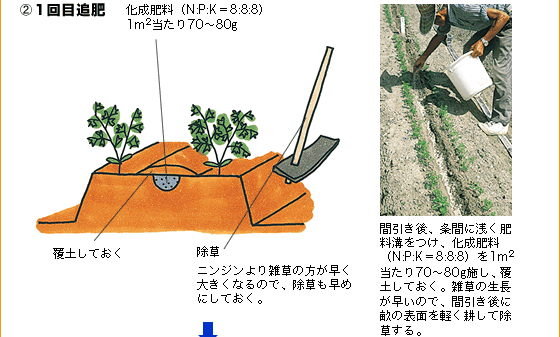
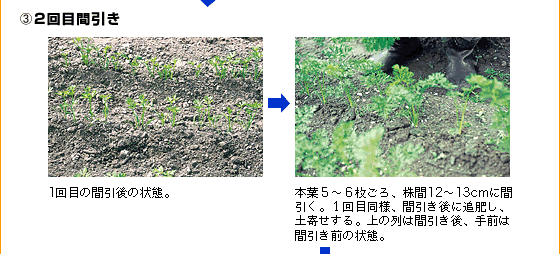
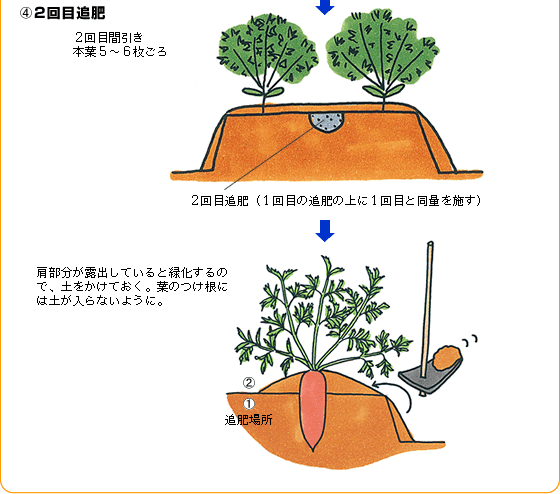
病害や生育障害
苗立枯病は、1回目の間引きを早くしないことで対応します。菌核病、うどんこ病などは早期防除に努めます。害虫では、特にアゲハの幼虫が好んで食害するので注意しましょう。

ニンジンを好んで食害するアゲハの幼虫。

連作などが原因で発生したネコブセンチュウによる被害。

生育後期に乾燥と過湿を繰り返した場合、裂根しやすいので注意する。
収穫
五寸ニンジンは、タネまき後110〜130日を目安に収穫します。極端に収穫が遅れると、品種によってはひどく裂根することがあります。